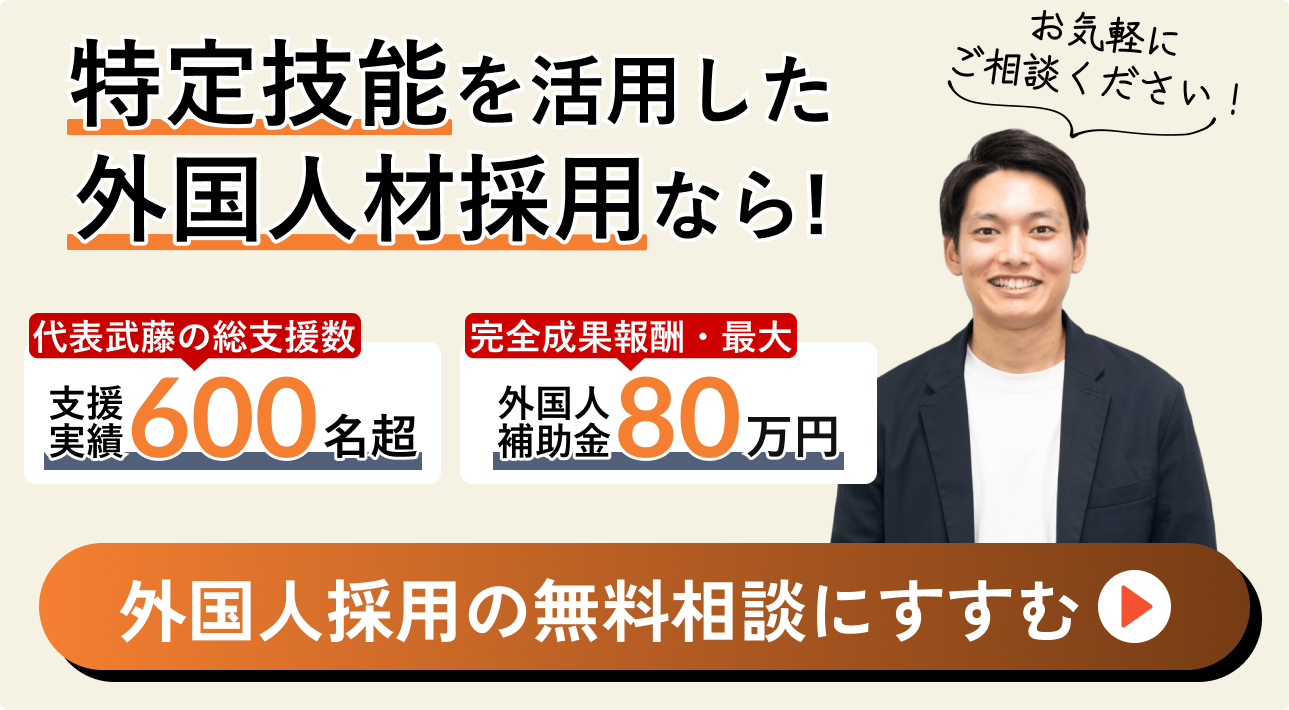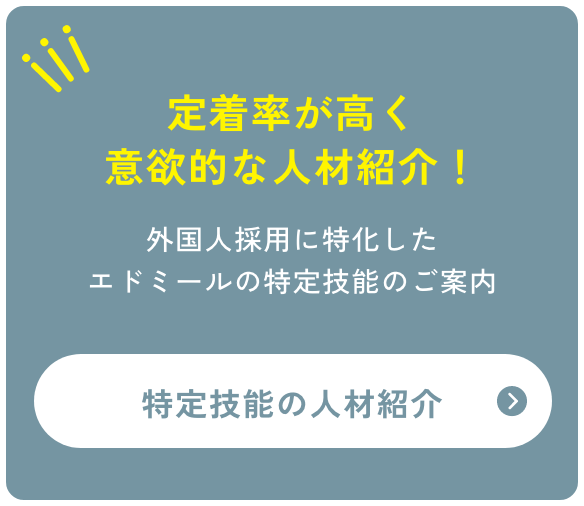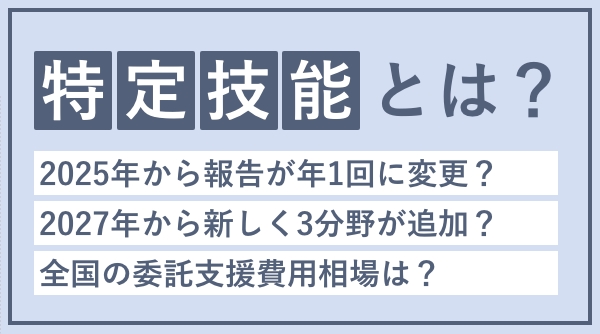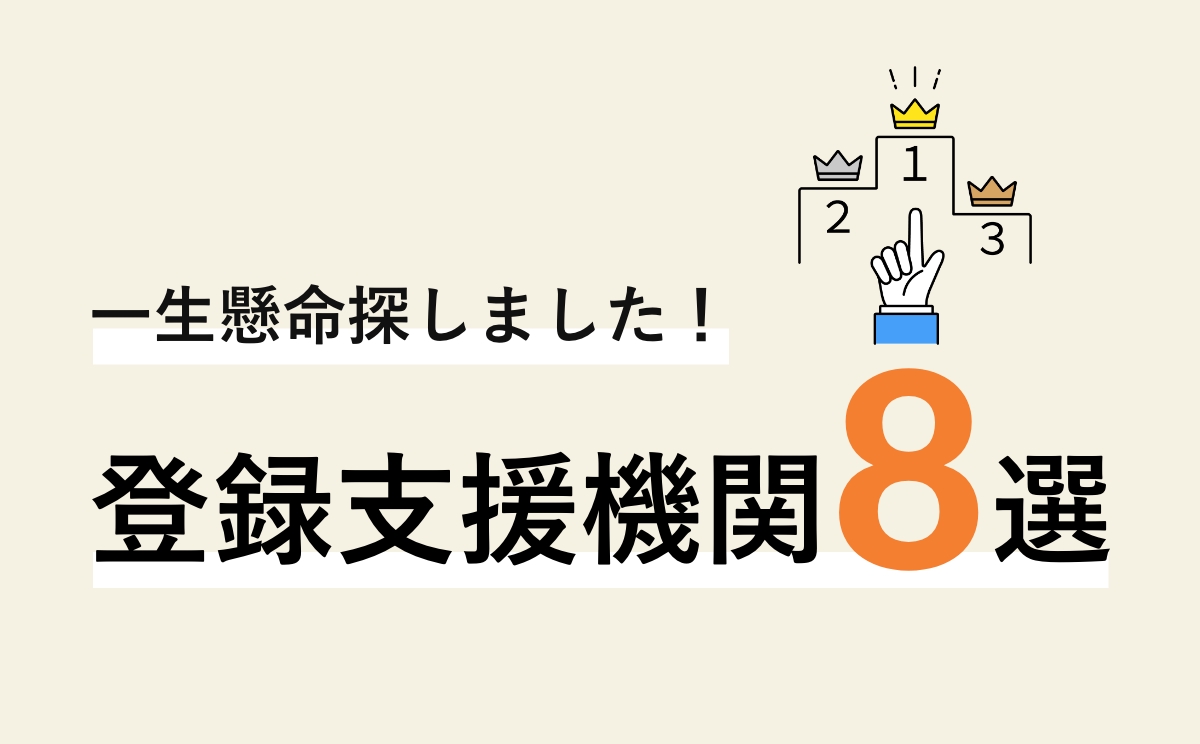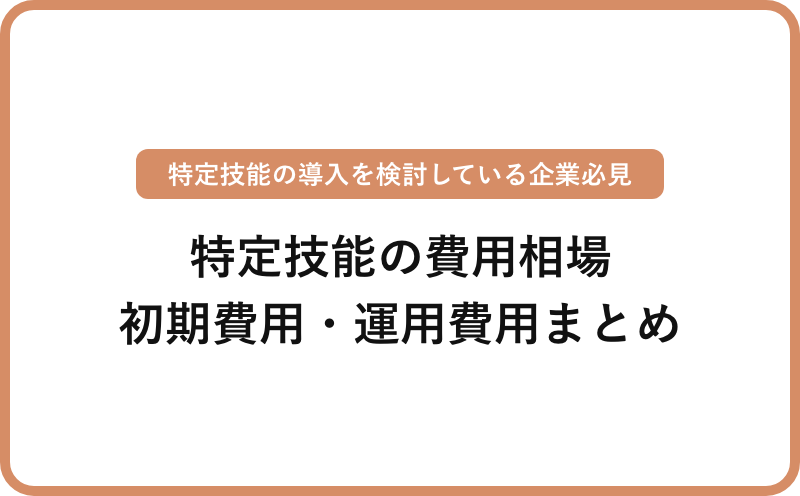登録支援機関と行政書士の関係とは?申請手続きや支援内容をわかりやすく解説
更新
特定技能制度の導入により、外国人材の受け入れを検討する企業が増える中、「登録支援機関」の役割が注目されています。そして、支援機関の申請や運営に深く関わる専門家が行政書士です。
本記事では、登録支援機関の基礎知識から、行政書士の業務内容、支援内容、申請プロセス、さらには「申請等取次制度」の仕組みまでをわかりやすく解説します。外国人雇用を検討中の企業担当者や、支援機関設立を考える専門家の方はぜひ参考にしてください。

合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢
2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。
武藤 拓矢のプロフィール登録支援機関とは?
登録支援機関とは、日本で働く「特定技能」外国人を受け入れる企業に代わって、生活支援や行政手続きの補助などを行う民間または公的な機関です。
特定技能制度では、外国人が円滑に就労・生活できるように、14項目に及ぶ「義務的支援」が企業側に課されています。しかし、全てを自社で対応するのは難しい企業も多いため、外部の登録支援機関を活用するケースが増えています。
登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁(入管庁)への申請と審査が必要であり、継続的に支援体制の整備や報告義務を果たすことも求められます。
行政書士の役割と業務内容
行政書士は、主に官公署への許認可手続きを専門とする国家資格者であり、登録支援機関の設立・運営においても重要な役割を担っています。具体的な業務内容は以下の通りです。
- 登録支援機関の申請書類作成・提出
- 特定技能に関する「申請等取次」手続きの代行
- 外国人就労に関する法令相談・指導
- 在留資格変更・更新・認定などのサポート
特に「申請等取次行政書士」に登録している場合、企業や登録支援機関に代わって入管への出頭なしで在留資格手続きを進めることができ、大きな時間と労力の削減につながります。
外国人雇用に関する手続きと支援内容
特定技能外国人の雇用に際して、企業は以下のような手続きを行う必要があります。
- 事前ガイダンスの実施(労働条件・生活ルールの説明)
- 入国時の送迎と住居確保
- 日本語学習の支援
- 生活相談体制の整備
- 定期面談・報告書の作成・提出
これらは「義務的支援」と呼ばれ、企業が自ら行うことも、外部の登録支援機関に委託することも可能です。
行政書士事務所が登録支援機関として活動する場合、法的手続きの知見と書類作成能力を活かし、支援業務を円滑に行う体制を整えています。
登録支援機関の申請プロセスと注意点
登録支援機関として認可を受けるためには、以下のプロセスを踏む必要があります。
- 要件確認(欠格事由がないか、過去の違反歴など)
- 申請書類の準備(支援計画書、体制図、契約書の雛形など)
- 出入国在留管理庁への提出
- 審査(平均1〜2ヶ月)
- 登録完了(認定番号の発行・公表)
申請には不備がないよう細心の注意が必要であり、書類の記載ミスや支援体制の不備があると不許可になることもあります。
このようなリスクを回避するためにも、行政書士に依頼することで、専門的かつ法令遵守の視点から申請をサポートしてもらうことが推奨されます。
よくある質問
- Q. 行政書士は必ず登録支援機関にならないといけませんか?
- A. 必須ではありませんが、行政書士事務所が登録支援機関として登録しているケースも多く、外国人支援の包括的対応が可能になります。
- Q. 行政書士に依頼するメリットは何ですか?
- A. 申請等取次制度を活用し、煩雑な入管手続きを代行してもらえる点や、書類作成・法的リスクへの対応力が高い点が挙げられます。
- Q. 登録支援機関の申請はどれくらいの費用がかかりますか?
- A. 行政書士への報酬相場は10万円〜30万円程度で、事務所によって異なります。別途、顧問契約や支援業務委託料がかかる場合もあります。
- Q. 行政書士と社労士の役割の違いは?
- A. 行政書士は入管手続き・支援体制の構築を担当し、社労士は雇用契約・社会保険・労働基準関係を中心に対応します。特定技能においては連携することも多いです。