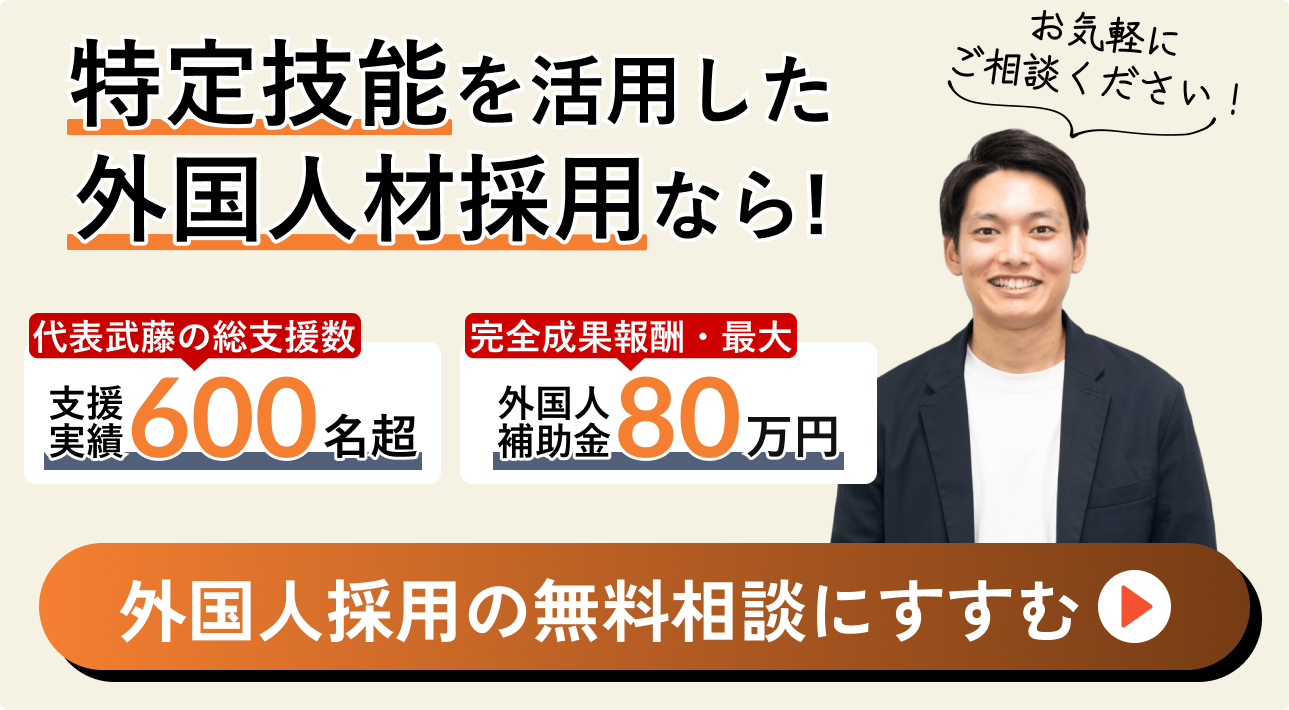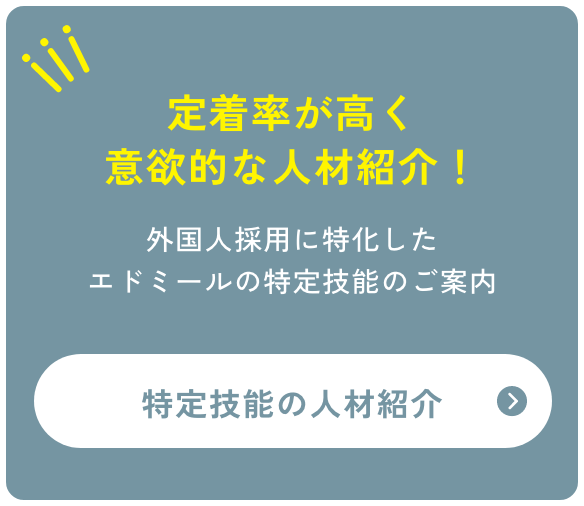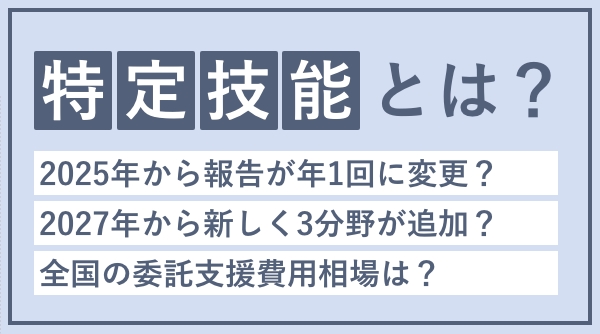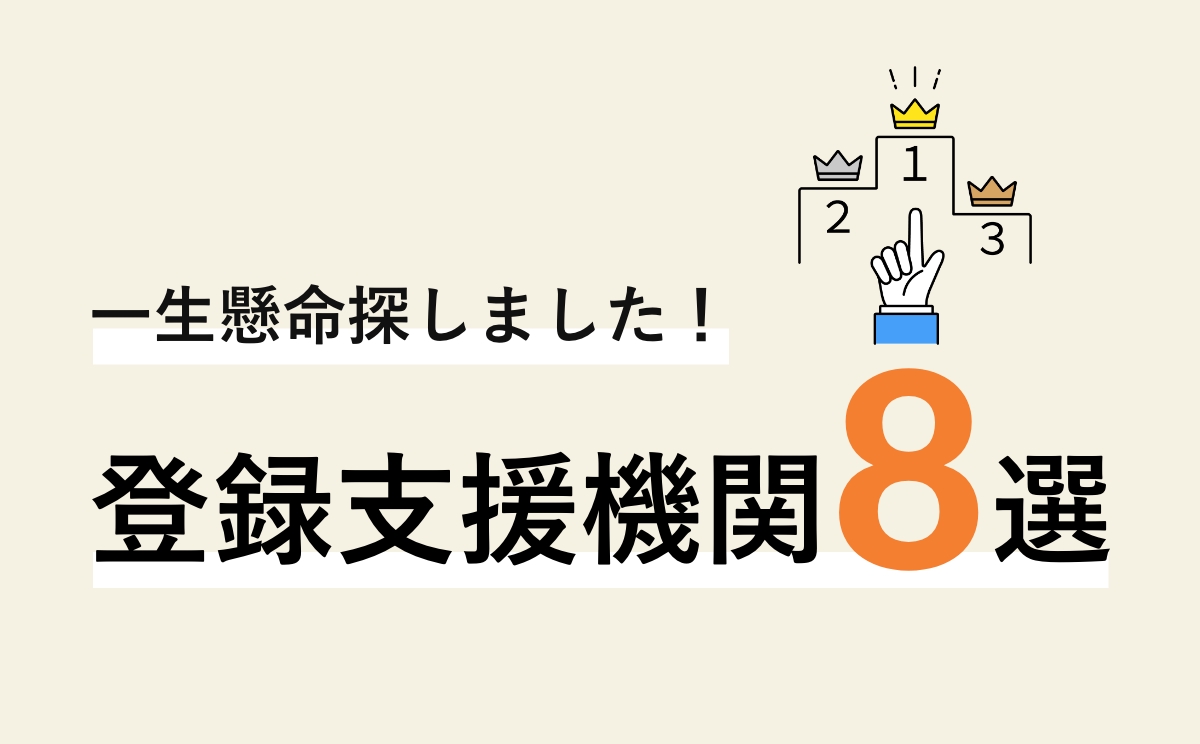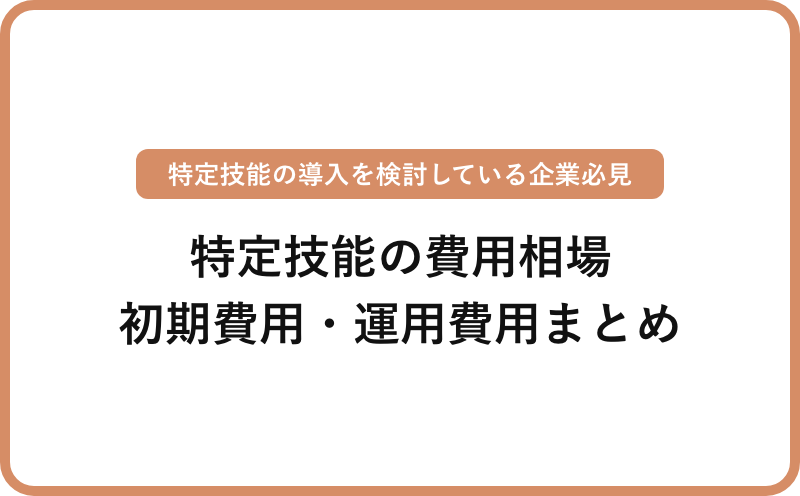登録支援機関への一部委託とは?制度・メリット・注意点をわかりやすく解説
更新
「自社で支援できる部分は対応したいけど、すべては難しい…」そんな企業に注目されているのが、登録支援機関への支援業務の一部委託です。
2024年の制度改正により、義務的支援10項目を一部だけ外部に委託できる制度が整備され、企業ごとの柔軟な支援体制構築が可能になりました。
この記事では、登録支援機関の基本概念から、一部委託制度の仕組み・メリット・注意点・登録支援機関の選び方まで、2026年の最新情報をもとにわかりやすく解説します。

合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢
2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。
武藤 拓矢のプロフィール登録支援機関の基本概念
登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業に代わって、生活支援・就労支援を実施する民間事業者です。
制度上、企業が「支援計画書」を提出する必要があり、その内容に沿って10項目の義務的支援を実施する必要があります。登録支援機関は、その支援実務の代行を担います。
登録支援機関の要件と基準
登録支援機関になるには、以下の要件を満たし、出入国在留管理庁の登録を受ける必要があります:
- 外国人支援業務に関する実績・体制を持つこと
- 過去に入管法違反・労働法違反がないこと
- 複数名の支援担当者が在籍していること
- 通訳・翻訳対応が可能なこと
登録後も定期的な届出や監査があり、一定の支援品質が維持されていることが前提です。
支援業務の委託について
企業が支援計画を自社で作成し、一部の支援業務だけを登録支援機関に外部委託することが可能です(2024年改正で制度化)。
一部委託が可能な業務例:
- 定期面談の実施・記録・届出
- 住居確保・生活契約支援
- 日本語学習機会の提供
- 出入国時の送迎
一部を自社、残りを登録支援機関に委託することで、コストと人的リソースを最適化できます。
登録支援機関に委託するメリット
- 支援義務の法的リスクを軽減:専門機関が制度に準拠して対応
- 母国語対応・通訳体制の確保:自社では難しい言語対応をカバー
- 支援計画の作成・管理を効率化:書類作成や届出も任せられる
- 必要な部分だけ外注できる:自社の強みに応じた柔軟な体制構築が可能
登録支援機関の選び方
委託先を選ぶ際には、以下のポイントをチェックしましょう:
- 対応可能な支援項目:すべて対応可能か、一部だけか
- 対象国籍と母語サポート:自社で受け入れている国籍に対応しているか
- 実績と届出の正確さ:入管庁への届出経験が豊富か
- 料金体系が明確:業務ごとに料金が分かれているか
比較サイトや入管庁の公開リスト、口コミなども参考にしつつ、相見積もりを取るのが安心です。
委託に関する注意点
- 契約書は必ず業務ごとに内容を明記:委託範囲を曖昧にしない
- 定期面談など実施義務の時期に注意:支援が抜けると制度違反になる
- 記録保存の責任分担を明確化:どちらが記録管理するかを契約書に記載
一部委託は便利な反面、委託内容と責任範囲を明確にしておかないとトラブルの元になります。
登録支援機関の最新情報と動向
2026年現在、登録支援機関の数は全国で11,000件以上。中でも一部委託に柔軟に対応できる中小機関や多言語対応に強い事業者が増加しています。
また、支援の外注需要が高まる中で、「面談だけ委託」「住居支援だけ外注」などのニーズも拡大。今後は、特定技能の分野別・国籍別に特化した支援機関がさらに台頭してくると見られます。
まとめと今後の展望
登録支援機関への一部委託は、支援体制の柔軟性を高める制度的選択肢として非常に有効です。
制度を正しく理解し、企業の強みと弱みを見極めて支援体制を設計することで、特定技能外国人との信頼関係を築き、定着率の向上にもつながります。
今後は、複数の登録支援機関との連携や、外国人材管理のデジタル化などを取り入れながら、より持続可能な受け入れ体制が求められていくでしょう。