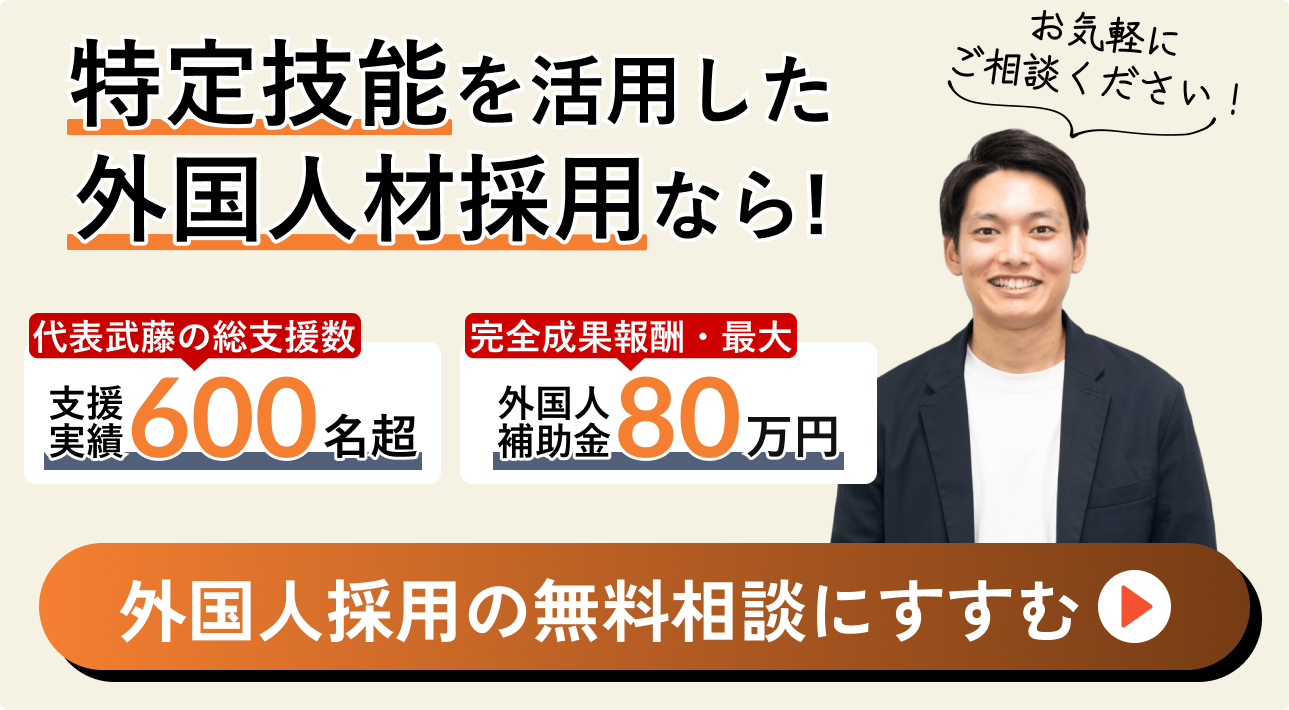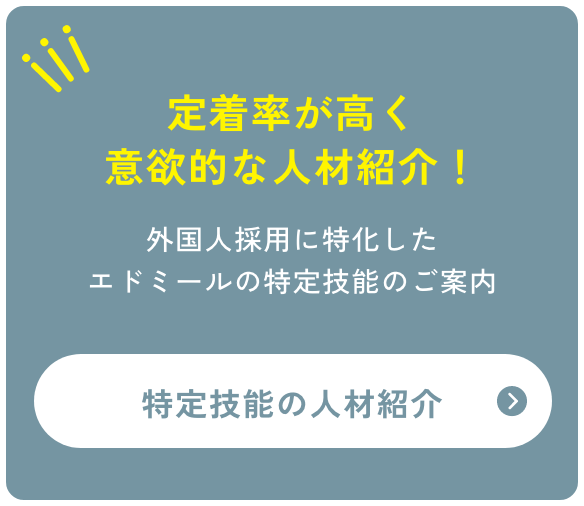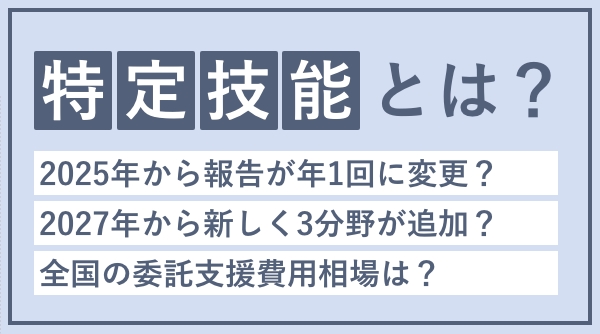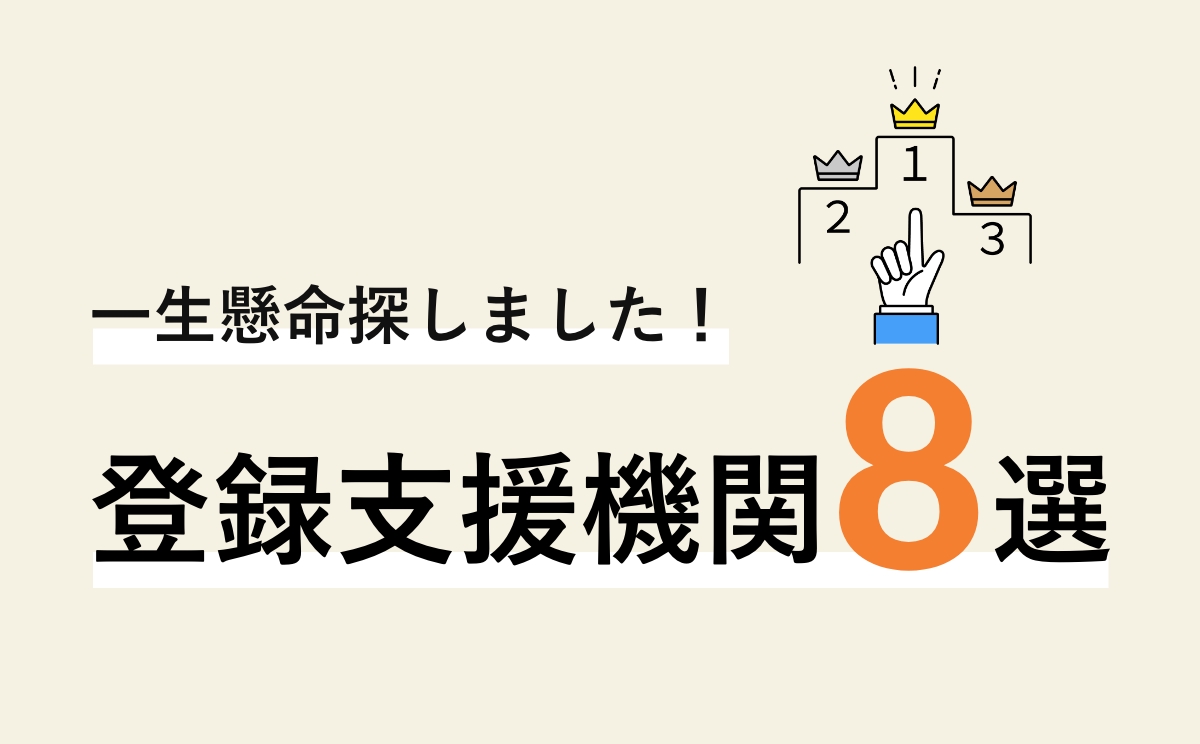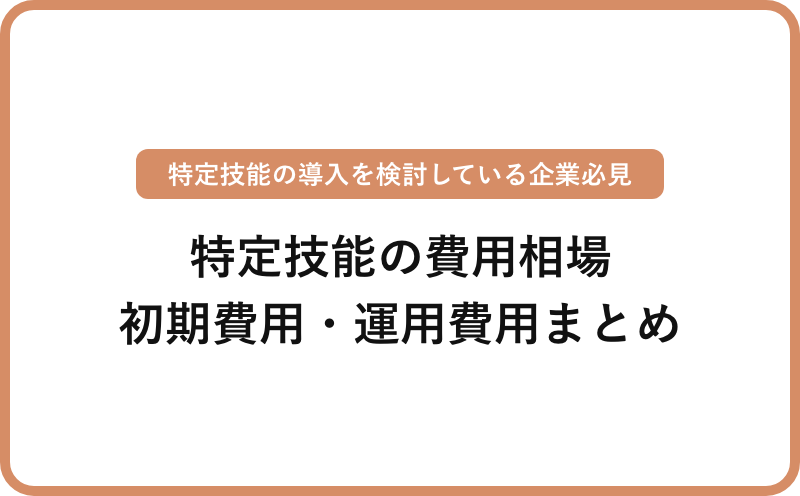在留資格「介護」と特定技能「介護」の違いとは?要件・期限・取得方法を徹底解説
更新
外国人介護人材を受け入れる上で、在留資格「介護」および特定技能「介護」の違いを理解することは非常に重要です。制度の取得要件、在留期間、転換方法、そして企業と本人のメリット・注意点を、最新動向を踏まえながら分かりやすく整理しました。

合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢
2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。
武藤 拓矢のプロフィール制度別の概要と立ち位置
在留資格「介護」は、介護福祉士の国家資格を取得した人が対象の制度です。一方、特定技能「介護」は、即戦力として技能試験と日本語要件(JLPT N4)に合格した外国人を受け入れる制度で、在留期間が最長5年と限定されています。
2025年4月からは、特定技能「介護」による訪問介護も解禁され、人手不足の在宅ケア市場にも外国人労働者を導入できる流れが進んでいます。
取得要件と転換条件
在留資格「介護」を取得するためには、介護養成施設を卒業し、国家試験合格が必要です。未合格の場合でも、再挑戦の在留延長が最大1年間認められています。
特定技能から介護ビザへ切り替えるケースは、特定技能「介護」の在留期間内に介護福祉士資格を取得することが条件。取得できれば、永続的な在留が可能になります。
在留期間と家族帯同の違い
特定技能「介護」は在留期間が最長5年(更新不可)で、家族帯同は原則不可です。一方、在留資格「介護」は更新可能で期間制限なく滞在でき、家族帯同も認められます。
また、永住権申請のための就労期間として「介護ビザ」での就業は有効ですが、特定技能歴は含まれません。
訪問介護の解禁と制度活用の拡大
2025年4月から、特定技能「介護」による訪問介護が解禁され、これまで施設のみ対象だった範囲が大きく広がりました。在宅介護事業者にとっては外国人雇用の新たな可能性が開けています。
ただし訪問介護に従事するには、一定の経験・技能・日本語力が求められ、自治体による運用方針も要確認です。
企業・施設側のメリットと留意点
外国人に介護福祉士資格を取得させることで、施設は介護保険制度による報酬アップ(認定加算)や定着率の向上が期待できます。また、家族帯同対応や長期人材活用も可能です。
一方で、試験対策・日本語研修・資格取得支援の導入にはコストや体制整備が必要。また、資格不合格者の在留延長や転換失敗によるリスクもあり、適切な支援体制が求められます。
外国人本人にとってのメリットと注意点
介護ビザ取得者は家族帯同が可能になり、安定して滞在可能です。キャリアアップや昇給機会も増え、永住申請にも近づくメリットがあります。
ただし、介護福祉士国家試験の受験には高い日本語力と知識が求められ、語学・試験準備への支援が不十分だと離職リスクにつながります。
特定技能での訪問介護従事条件
訪問介護に従事する特定技能1号者は、現場経験や日本語能力の要件が強化されています。厚労省指針により、一定の研修や日本語テストが義務付けられています。
自治体ごとに対応要件が異なるため、事前に確認し登録支援体制を整備することが重要です。
まとめ|制度の違いを理解し、将来的なキャリア設計を支援しよう
在留資格「介護」と特定技能「介護」には明確な違いがあり、制度の選択や転換には慎重な判断が必要です。企業は適切な支援体制を整備し、資格取得支援を通じて長期定着を図る体制構築を目指すべきです。
外国人材側も、資格取得と制度選択の理解を深めることで、日本でのキャリア形成を戦略的に設計できます。