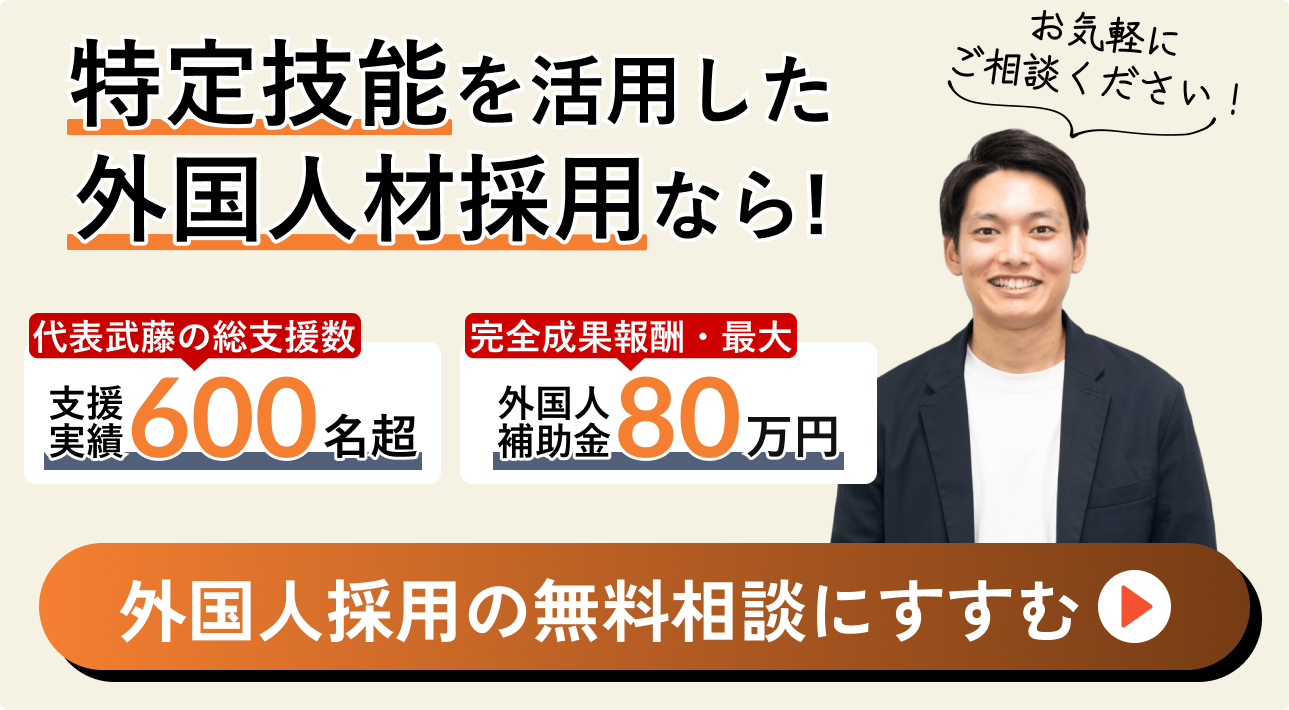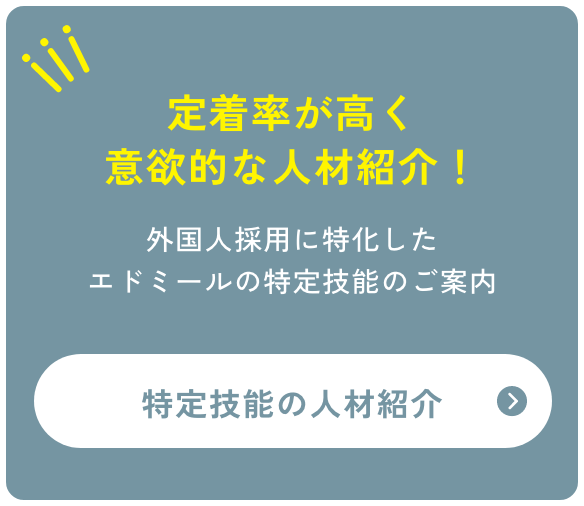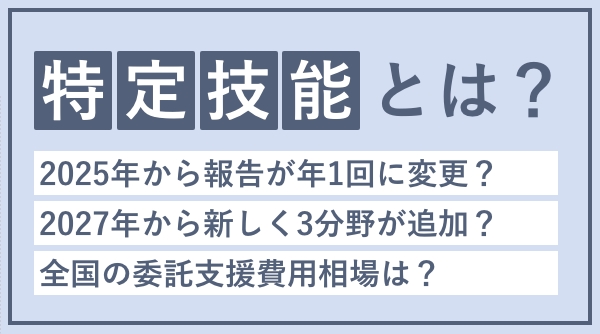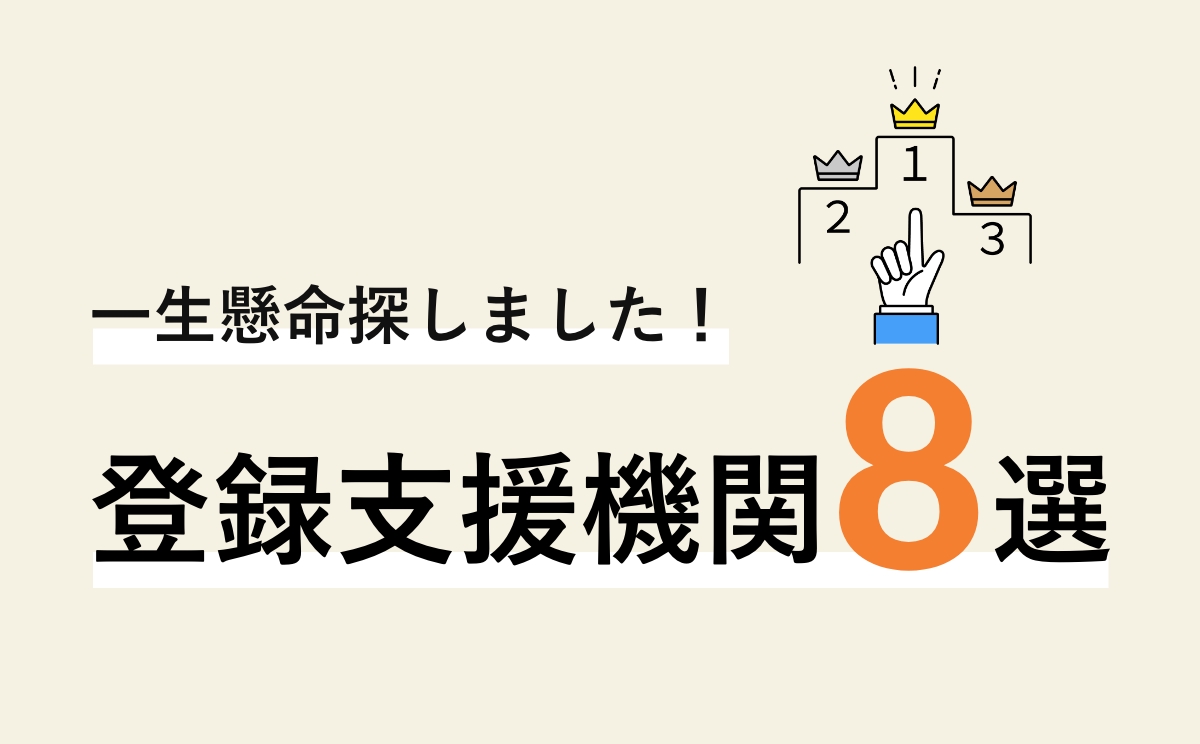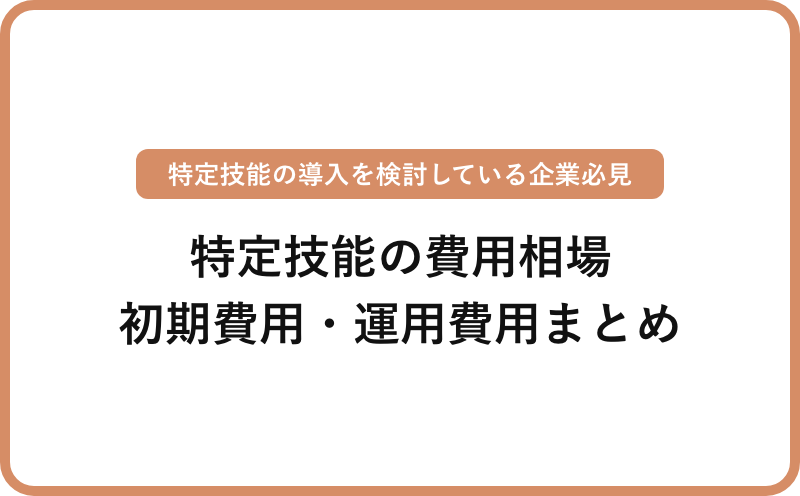【2026年対応】特定技能外国人の受け入れ方法と注意点を徹底解説|制度概要から手続き・雇用管理まで
更新
少子高齢化と人手不足が深刻化する中で、即戦力となる外国人材の受け入れ制度として注目されているのが「特定技能制度」です。
「どのような手続きが必要なのか」「自社でも雇用できるのか」「制度上のリスクはないか」など、多くの企業担当者が疑問を抱えているのではないでしょうか。
本記事では、2026年現在の制度に基づき、特定技能制度の概要・受け入れフロー・雇用時の注意点・よくある質問までわかりやすく解説します。

合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢
2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。
武藤 拓矢のプロフィール特定技能制度の概要
特定技能制度とは、深刻な人手不足に直面する14分野において、即戦力となる外国人材の就労を認める在留資格制度です。
制度には2種類あります:
- 特定技能1号:14分野に対応し、在留期間は通算5年まで。家族の帯同は不可。
- 特定技能2号:現在は2分野(建設・造船)に限定。在留期間の上限なし、家族帯同可。
日本語能力試験(N4以上)と分野別技能評価試験に合格した外国人が対象となります。技能実習からの移行も多く、即戦力性が高い制度です。
特定技能外国人の受け入れ手続き
受け入れの主なステップは以下の通りです:
- ① 人材募集
海外の送り出し機関や登録支援機関、求人サイトを通じて候補者を募集します。 - ② 面接・内定
Web面接または現地面接を実施し、内定通知を出します。 - ③ 在留資格の申請
「特定技能1号」または「2号」の在留資格認定証明書を出入国在留管理局に申請します。 - ④ 支援計画の作成・提出
義務的支援10項目を明記した支援計画書を添付。 - ⑤ 入国・就労開始
空港送迎、生活支援、日本語支援を行い、就労スタート。
登録支援機関に一部または全部を委託することで、支援業務の負担を軽減することも可能です。
特定技能外国人の雇用に関する注意点
特定技能外国人の雇用にあたっては、以下のようなポイントに注意する必要があります。
✅ 労働条件の遵守
雇用契約は日本人と同等以上の待遇が義務付けられています(最低賃金・時間外手当・福利厚生など)。
✅ 支援義務の履行
受け入れ企業または登録支援機関は、10項目の義務的支援を計画に沿って実施する必要があります。
✅ 面談・記録・届出の管理
3か月に1回以上の面談実施と記録保存(1年以上)、年1回の定期届出が必須です(2025年以降の改正により統一)。
✅ 在留資格更新時の対応
更新手続きでは、支援実績・記録の提出を求められるため、日々の管理と記録が重要です。
特定技能外国人受け入れのよくある質問
Q. 特定技能外国人はどの国から受け入れられますか?
A. 日本と二国間協定を締結している国(フィリピン、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、ネパール、モンゴル、タイ、カンボジア、バングラデシュなど)からの受け入れが一般的です。
Q. 特定技能外国人の在留期間は最長何年ですか?
A. 特定技能1号は最長5年、特定技能2号は制限がなく、更新可能です。
Q. 自社支援と登録支援機関のどちらが良いですか?
A. 支援体制や言語対応に自信がある場合は自社支援も可能ですが、多くの企業はコストと体制の観点から登録支援機関に委託しています。
Q. 支援記録や届出を忘れるとどうなりますか?
A. 支援不履行や記録不備は行政指導や登録取消の対象になります。支援責任者の設置と体制強化が求められます。
特定技能外国人受け入れまとめ
特定技能制度は、即戦力となる外国人材を受け入れるための制度として、多くの業界で活用が進んでいます。
ただし、支援義務・制度理解・記録管理など、受け入れ企業側に求められる責任も大きく、形式だけではなく実質的な運用が求められます。
2026年の制度改正(定期届出の年1回化など)にも対応しながら、制度への適正な理解と運用に努め、外国人材の安定就労と企業の発展を両立させていきましょう。