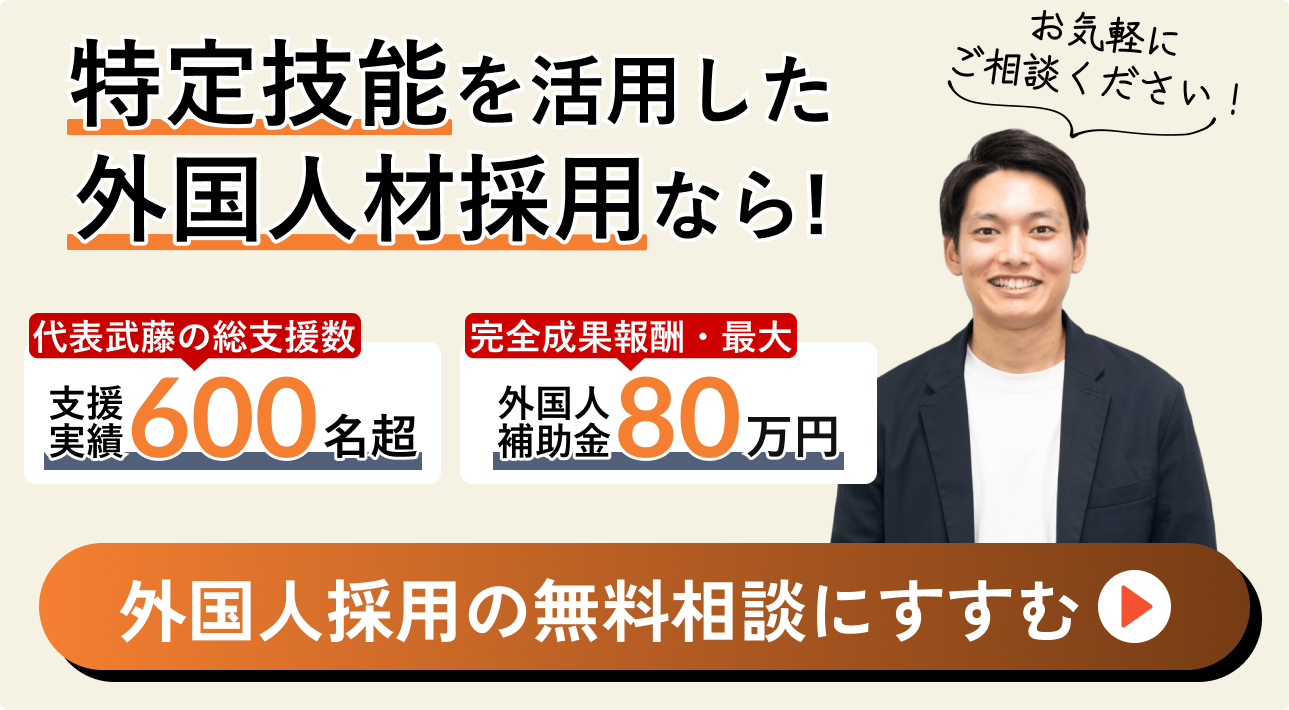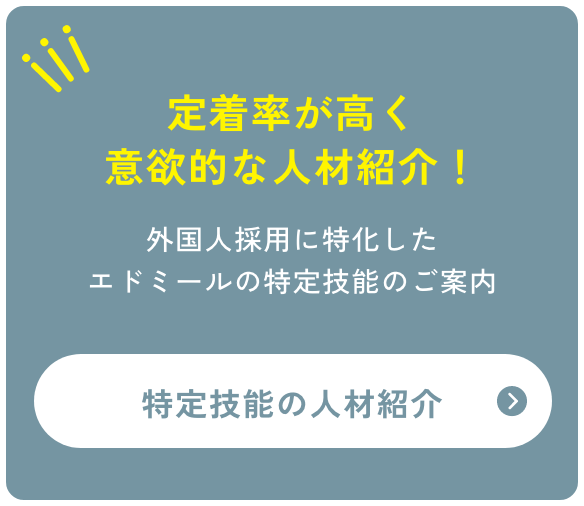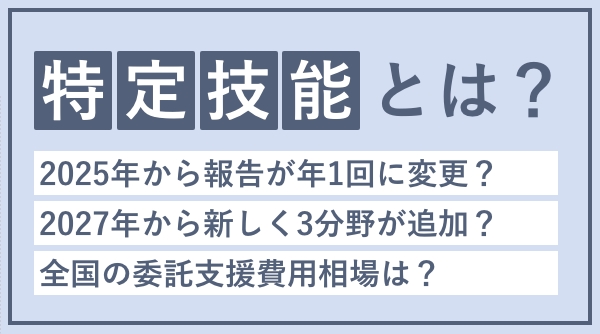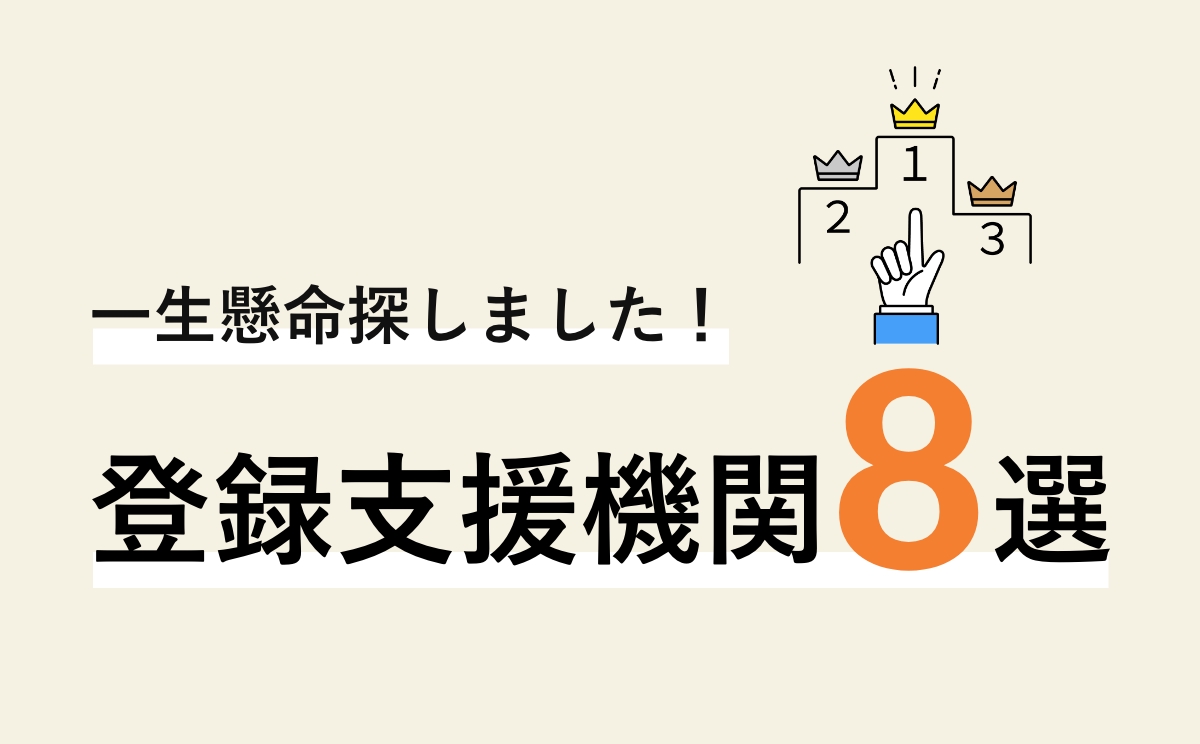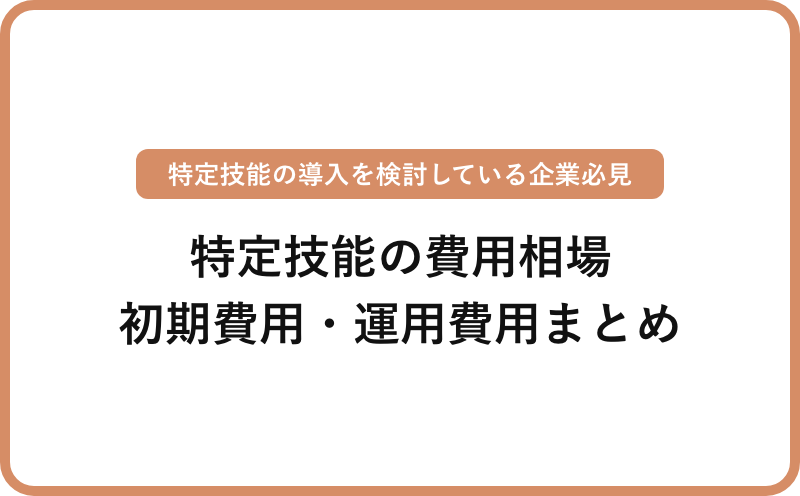【2026年版】特定技能で採用できる国一覧と特徴|受け入れ方法・試験制度も解説
更新
特定技能制度の活用が進む中、「どの国の外国人を採用できるのか?」という疑問を持つ企業担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では、特定技能外国人を受け入れ可能な国とその特徴、採用までの流れ、試験制度の現状を解説します。

合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢
2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。
武藤 拓矢のプロフィール特定技能外国人を採用できる国の一覧と特徴
特定技能制度では、制度上すべての国籍の外国人が対象です。ただし、実務上は日本と「二国間協定(MOC)」を締結している国の外国人の採用が推奨されています。
2026年現在、二国間協定が結ばれている主な国は以下のとおりです。
| 国名 | 特徴・傾向 |
|---|---|
| フィリピン | 英語力が高く、介護・建設・飲食業で人気 |
| ベトナム | 技能実習からの移行が多く、製造・外食に強み |
| インドネシア | イスラム教徒が多く、清真対応が必要な場合も |
| ミャンマー | 真面目で就労意欲が高い。農業・宿泊業に多い |
| カンボジア | 若年層の応募が多く、外食業との相性が良い |
| ネパール | 介護・宿泊・食品分野に多く、就学経験者も多数 |
| モンゴル | 寒冷地対応ができるため北海道などで人気 |
| スリランカ | 飲食・ビルクリーニング分野での応募が増加中 |
| タイ | 自動車整備や機械関連分野に実績あり |
| バングラデシュ | 技能実習経験者が多く、外食・建設に強み |
このほか、中国、ウズベキスタン、パキスタン、キルギス、ラオスなども協議対象国として増加傾向にあります。
協定国からの採用は制度トラブルが少なく、母国政府による送出管理がされている点でも安心とされています。
特定技能外国人の採用方法と流れ
採用の流れは以下のとおりです:
- ① 採用国と分野の決定(協定国が望ましい)
- ② 登録支援機関や海外送出機関への依頼
- ③ 候補者の技能・日本語試験の確認
- ④ 面接・内定(オンライン面接が主流)
- ⑤ 在留資格申請と支援計画書提出
- ⑥ 入国・就労開始
すでに在日している技能実習修了者を採用する場合は、在留資格変更申請での対応が一般的です。
特定技能に関する試験情報と動向
特定技能1号を取得するには、以下の2つの試験に合格する必要があります:
- 技能評価試験: 分野ごとの業務能力を測る(例:介護、農業、外食など)
- 日本語試験: JLPT N4またはJFT-Basicのいずれか
試験は日本国内および海外(協定国中心)で実施されています。ベトナム・フィリピン・インドネシアなどでは定期的に開催され、応募者数が増加傾向です。
また、技能実習2号修了者は、同分野に限り試験免除で申請可能なため、実習制度からのスムーズな移行が期待されています。
特定技能外国人の国籍についてのよくある質問
Q. どの国籍でも受け入れ可能ですか?
A. 制度上は可能ですが、原則として二国間協定を締結している国からの採用が推奨されています。
Q. ネパール人やベトナム人の割合が多いのはなぜですか?
A. 技能実習からの移行者が多く、日本語教育が浸透している国だからです。
Q. 非協定国から採用する場合のリスクはありますか?
A. 送出管理が不十分で、トラブルや不適切な仲介が発生しやすいため、慎重な判断が必要です。
Q. 採用国によって必要な対応は変わりますか?
A. 宗教(ハラール対応)、食文化、日本語レベルなどが国ごとに異なるため、受け入れ準備を柔軟に調整する必要があります。
特定技能外国人の国まとめ
特定技能制度は、世界中の即戦力人材を受け入れることが可能な柔軟な制度ですが、現実的には「協定国」からの採用が基本となっています。
国によって文化・能力・言語対応が異なるため、分野と国籍の相性を理解したうえで、支援体制を整えることが重要です。
登録支援機関や海外の送出機関と連携し、信頼できるルートでの採用・支援体制の構築を心がけましょう。