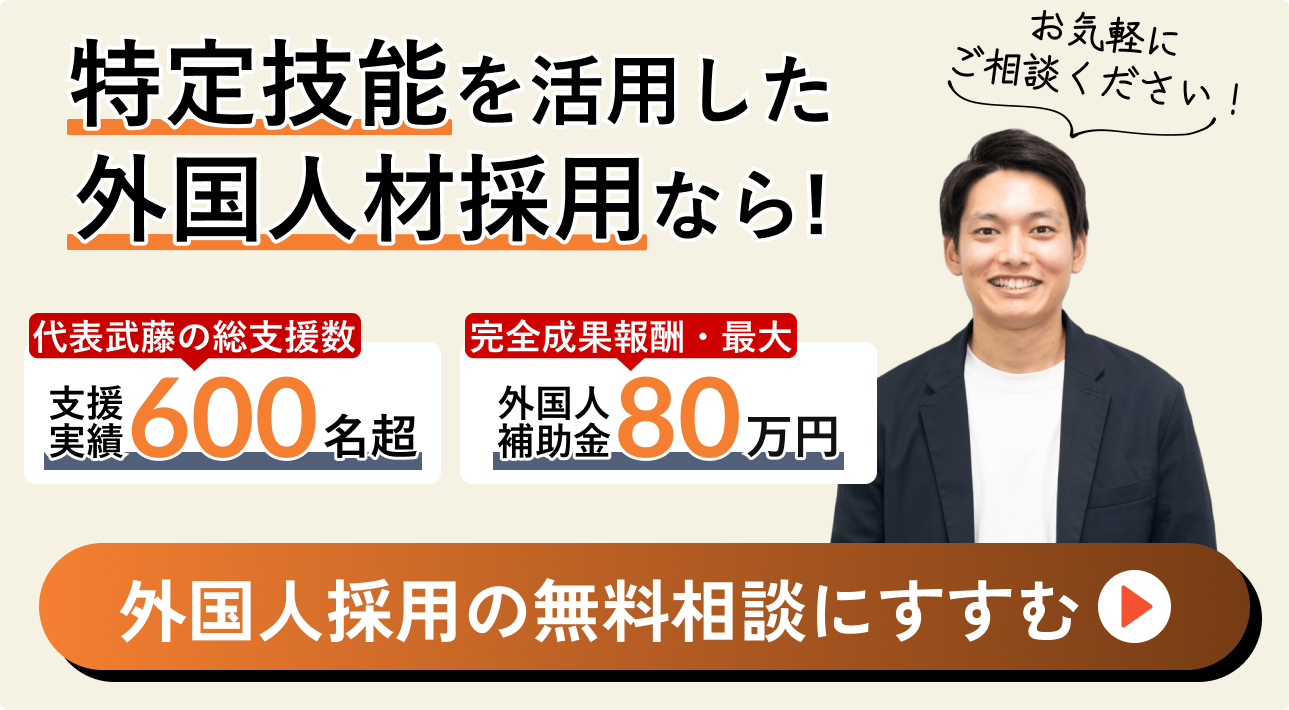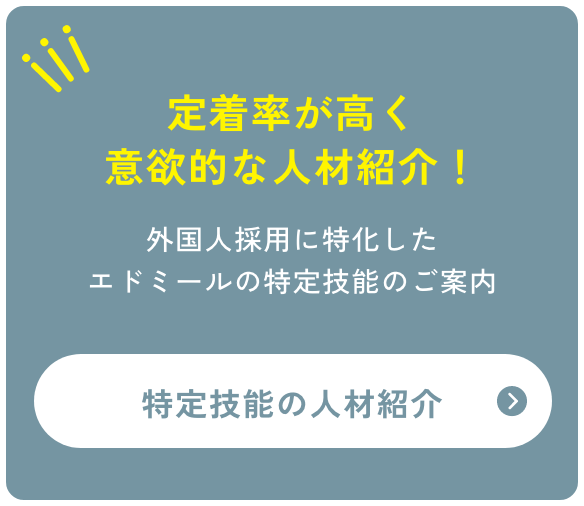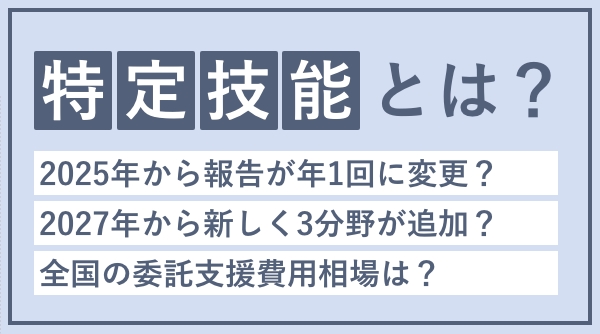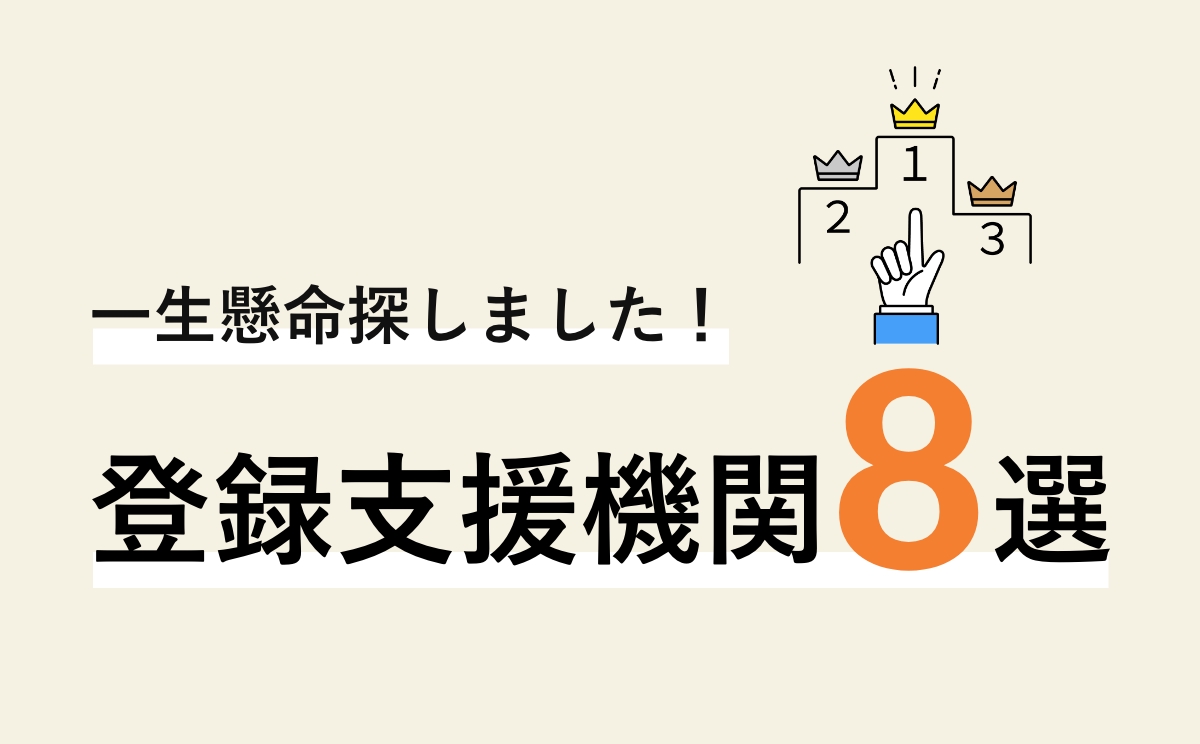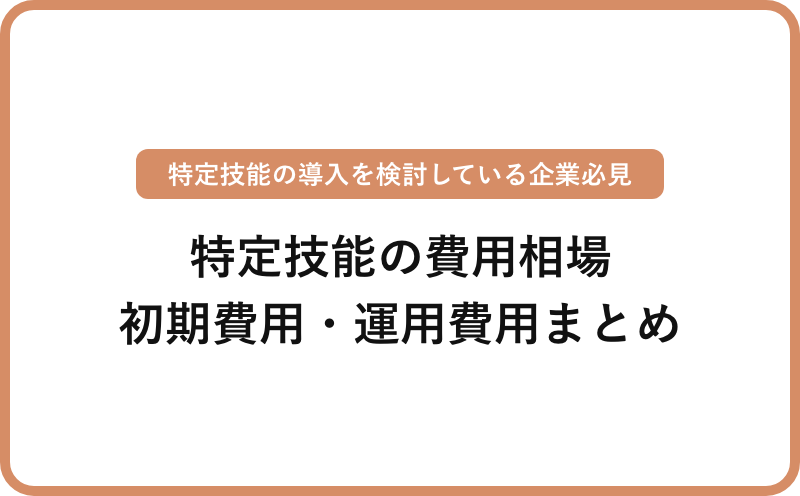【2026年対応】特定技能の定期面談ガイド|頻度・項目・報告義務まで徹底解説
更新
特定技能1号外国人の受け入れには、就労支援の一環として「定期面談」の実施が義務付けられています。業務や労働条件、生活状況の確認を行い、外国人が安心して働き続けられる環境を整えるために不可欠な支援です。
しかし、「面談の頻度は?」「記録はどうする?」「オンライン面談でも大丈夫?」といった疑問を抱える担当者も多いのではないでしょうか。本記事では、面談の実施方法から確認項目、制度改正後の最新ルール、報告義務までをわかりやすく解説します。特定技能の制度運用に不安のある企業担当者はぜひご一読ください。

合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢
2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。
武藤 拓矢のプロフィール特定技能の定期面談とは何か?
特定技能1号外国人を雇用する企業や登録支援機関には、定期的に本人との面談を実施し、就労環境や生活状況を把握する義務があります。これは外国人が安心して働き続けられる環境を維持するために欠かせない制度であり、出入国在留管理庁への報告も求められています。
面談は、制度上の「義務的支援」に含まれており、怠ると行政指導や登録支援機関の登録取消といったペナルティの対象となることもあります。適切な形式・頻度での実施が重要です。
定期面談の実施方法
面談の頻度とスケジュール
定期面談の実施頻度は、一般的には「四半期ごと(3か月に1回)」または「月1回」が目安とされています。ただし、実際の運用では業務の繁閑や特定技能外国人の状況に応じて柔軟な対応も認められています。
企業や支援機関は、事前にスケジュールを共有し、面談の計画性を保つことで、支援の質を維持することができます。
面談の形式(対面・オンライン)
2025年4月の制度改正により、面談の実施形式は対面だけでなく、オンラインや電話での実施も認められるようになりました。これにより、地理的・時間的な制約がある場合でも柔軟に対応可能となりました。
対面は非言語情報を含むコミュニケーションが可能で信頼関係を築きやすい一方、オンラインは移動時間の削減や遠隔地との接続が利点です。状況に応じた形式を選びましょう。
定期面談で確認すべき内容
業務内容に関する確認事項
面談では、特定技能外国人が担当業務を正しく理解し、日常的に問題なく遂行できているかを確認します。業務に対して不安や困りごとがないかを丁寧にヒアリングすることが重要です。
また、今後の業務目標やスキルアップの方向性についても共有し、本人のモチベーション維持とキャリア形成を支援する視点も大切です。
待遇や労働条件の確認
労働契約の内容と実際の就労状況に齟齬がないかを確認します。具体的には、給与・手当の支給状況、労働時間、休暇取得の有無などが対象です。
契約変更があった場合は、本人の同意が得られているか、説明が十分だったかも確認しましょう。待遇に対する満足度を把握することも、定着率向上に直結します。
生活環境や支援状況の確認
住居環境や交通手段、病院・買い物といった日常生活の利便性に問題がないかを確認します。生活の不安が業務にも影響することがあるため、生活面での支援も重要です。
加えて、地域イベントや日本人との交流状況をヒアリングすることで、社会的孤立を防ぐ支援策も検討できます。
定期面談での問題発覚時の対応
違反行為の種類と対処法
面談で就業規則違反やハラスメントなどの違反行為が判明した場合は、迅速かつ適切な対応が求められます。軽微な問題であれば注意喚起で済むこともありますが、重大なケースは是正措置や外部機関への相談が必要です。
問題の内容と本人の意見を丁寧に記録し、事後対応の方針を関係者と共有する体制が望まれます。
報告義務とその手続き
重大な問題が発生した場合には、出入国在留管理庁への報告義務が発生します。報告内容には、違反の概要、対応の経緯、再発防止策などが含まれます。
提出先や書式は地域の出入国在留管理局ごとに異なる場合があるため、最新のガイドラインを確認のうえ適切に対応しましょう。
定期面談を行う際の注意点
言語の選択と理解度の確認
面談は、特定技能外国人が理解できる言語で行うことが原則です。日本語能力に不安がある場合は、母国語や英語、または通訳の活用を検討してください。
一方的な説明ではなく、理解度を確認するための質問や双方向の対話を意識すると効果的です。
中立的な立場の担当者の重要性
面談の担当者は、特定技能外国人が安心して相談できるよう、中立的な立場であることが望ましいです。上司や現場責任者ではなく、第三者的立場の支援担当者が適任とされています。
信頼関係が築けることで、本音の意見を引き出しやすくなり、問題の早期発見・解決にもつながります。
定期面談の実施後の手続き
報告書の作成と提出
面談が終わったら、内容を記録した報告書を作成します。日付、場所、出席者、確認した事項、対応方針などを網羅的に記載しましょう。
報告書は、必要に応じて出入国在留管理庁への届出資料としても活用されるため、正確かつ丁寧な作成が求められます。
次回面談に向けた準備
今回の面談で得た情報をもとに、次回の面談に向けた改善事項や議題を整理しておきましょう。継続的な支援と信頼構築のためにも、事前準備は欠かせません。
資料の準備や本人への事前通知も行い、スムーズな実施につなげてください。
特定技能の定期面談に関するFAQ
Q. 定期面談はどれくらいの頻度で実施すべきですか?
A.定期面談は原則として、3か月に1回以上(=年4回以上)の実施が義務付けられています。これはすべての特定技能1号外国人に対して適用される基準です。
業務の状況や本人の事情に応じて、必要に応じてそれ以上の頻度で実施することも可能ですが、年1回などの低頻度では制度上の要件を満たしません。
Q. オンライン面談でも問題ありませんか?
A.はい、2025年の制度改正により、オンライン・電話での面談も正式に認められました。本人確認や記録の保存など基本的な要件を満たしていれば問題ありません。
Q. 面談内容はどこまで記録すべきですか?
A.「いつ、誰が、何を確認し、どう対応したか」を明確に記録してください。必要に応じて行政に提出する可能性もあるため、形式や内容に注意が必要です。
Q. 面談で問題が発覚した場合、誰に報告すべき?
A.登録支援機関の支援責任者や企業の管理者にまず報告し、必要に応じて地方出入国在留管理局へ届け出る義務があります。対応のスピードと正確性が求められます。
Q. 面談を行わなかった場合のペナルティは?
A.義務的支援の不履行と見なされるため、行政指導や登録支援機関の登録取消、受入企業の新規受入停止といった処分を受けるリスクがあります。