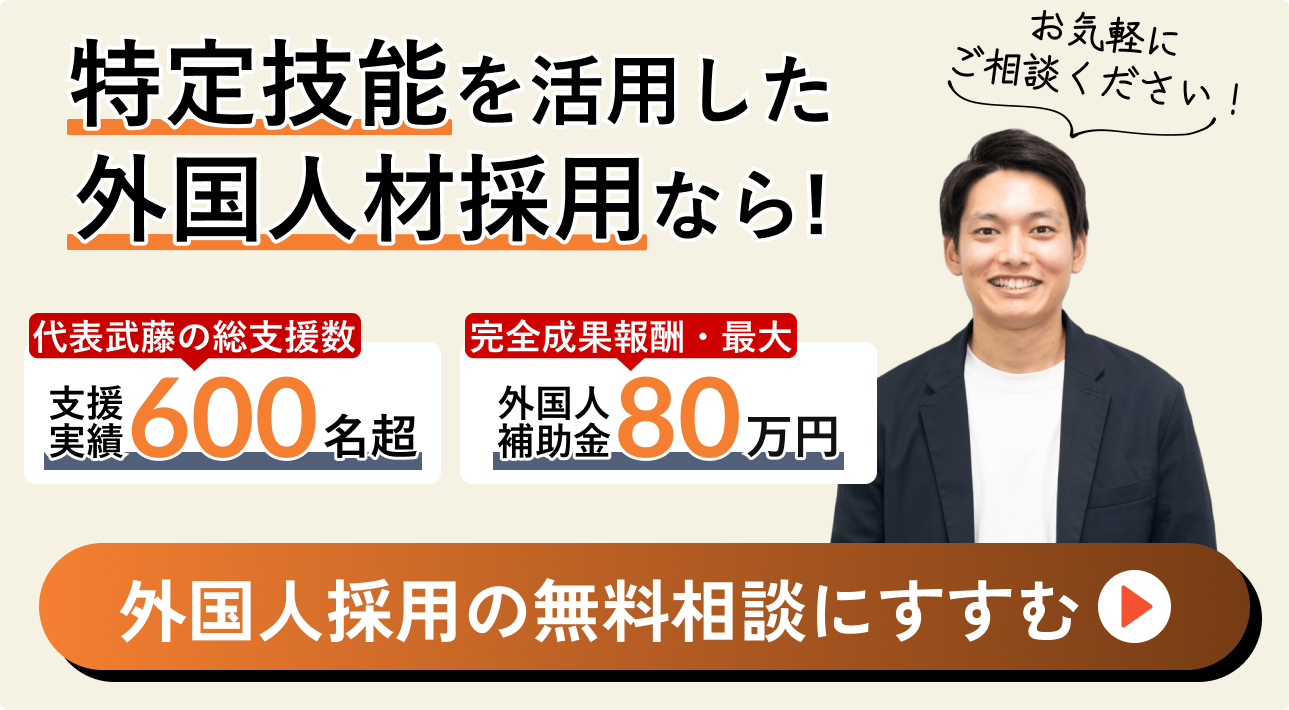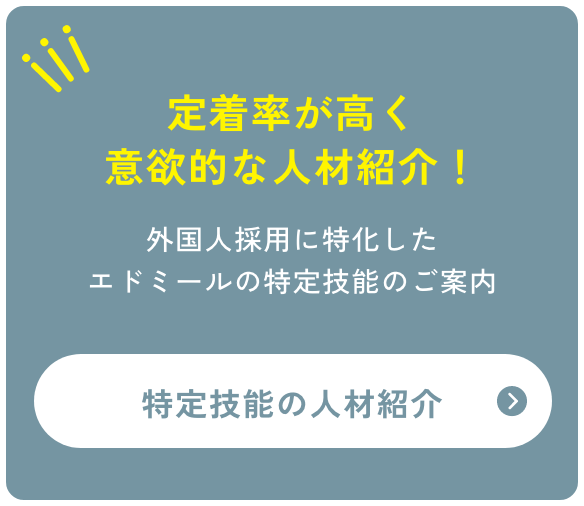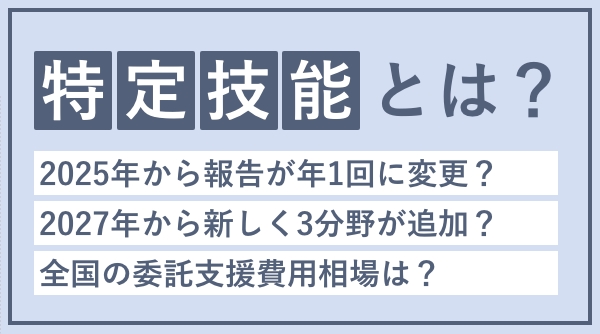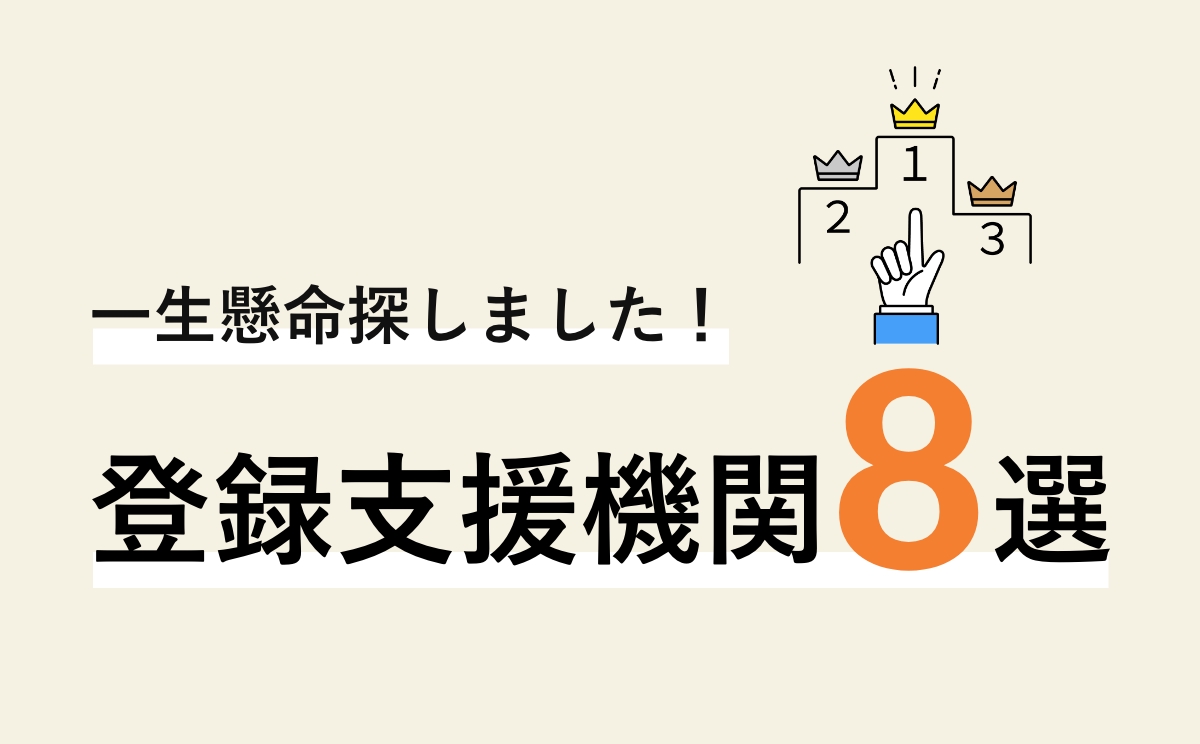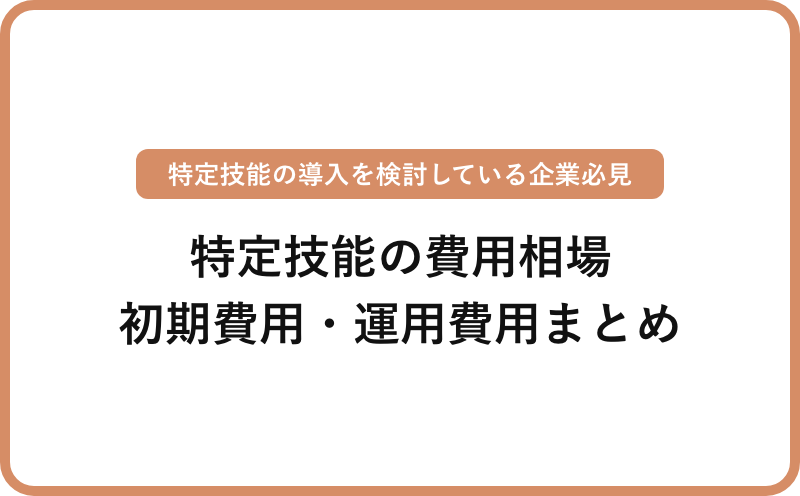【2026年最新版】特定技能制度のメリット・デメリットを徹底解説|受け入れ企業が知るべき実態と活用法
更新
人手不足が深刻化する中、外国人材の受け入れ手段として注目されているのが「特定技能制度」です。
本記事では、2026年時点での最新制度に基づき、特定技能の制度概要、メリット・デメリット、導入時の注意点や活用方法までをわかりやすく解説します。

合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢
2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。
武藤 拓矢のプロフィール特定技能制度の概要
特定技能制度は、2019年に新設された在留資格制度で、日本の人手不足が深刻な分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れることを目的としています。
2026年現在、特定技能には以下の2種類があります:
- 特定技能1号: 16分野で受け入れ可。在留期間は通算5年。家族帯同不可。
- 特定技能2号: 建設・造船など特定分野でのみ対応。在留期間無制限。家族帯同可。
主に技能実習修了者や、技能評価試験と日本語試験に合格した外国人が対象です。
特定技能外国人を受け入れるメリット
1. 即戦力人材の確保
特定技能は「労働力確保」を目的とした在留資格のため、実務経験や技能を持つ即戦力人材を採用できます。特に技能実習を修了した人材は、日本の職場環境にも慣れており定着しやすいです。
2. 受け入れ分野の幅広さ
2026年現在、介護・農業・建設・宿泊業・外食業など16分野で受け入れが可能となっており、様々な業界に対応しています。
3. 柔軟な雇用契約が可能
技能実習制度と異なり、労働契約の自由度が高く、転職も可能です。就労条件は日本人と同等以上であれば企業の裁量で設定できます。
4. コミュニケーション能力が高い
日本語能力試験(JLPT N4以上)またはJFT-Basicの合格が要件となっており、一定の日本語コミュニケーション能力を持つ人材を採用できます。
特定技能外国人受け入れのデメリット
1. 支援義務が重い
企業は特定技能1号の外国人に対して、10項目の義務的支援(生活支援・面談・通訳など)を提供しなければなりません。支援体制が整っていないと制度違反となります。
2. 文書管理の手間
支援記録、面談記録、支援計画書の作成・保存(1年以上)が必須です。更新や定期届出の際にも提出が求められ、社内管理体制が必要です。
3. 転職・退職のリスク
制度上、外国人は同分野内であれば転職が可能です。就労条件や職場環境に不満がある場合は早期離職に繋がるリスクもあります。
4. 日本語力・文化の差への対応
日本語N4レベルは日常会話に支障がない程度ですが、専門用語や業務指示の理解には限界があるケースもあります。また文化・宗教対応も必要です。
特定技能制度の活用方法
登録支援機関の活用
義務的支援の一部またはすべてを登録支援機関に委託することで、企業の負担を軽減できます。支援実績が豊富な機関を選ぶことが成功の鍵です。
技能実習制度との連携
技能実習からの移行者は、日本語と業務に慣れているため、特定技能として高い定着率が期待できます。実習→特定技能の導線構築が効果的です。
特定技能制度のよくある質問
Q. 特定技能と技能実習の違いは?
A. 技能実習は技能習得が目的で、実習期間終了後は原則帰国。一方、特定技能は就労目的で、更新・転職・永住への道もあります。
Q. 特定技能の在留期間は最長何年ですか?
A. 特定技能1号は最大5年(更新制)、2号は無期限で家族帯同も可能です。
Q. 支援義務は自社で全部行う必要がありますか?
A. 登録支援機関への委託も可能です。一部委託もできるため、自社の体制に応じて調整できます。
Q. 外国人の受け入れに補助金は使えますか?
A. 一部の自治体では外国人支援や通訳体制整備に対する補助金制度があります。都道府県の助成金情報を確認しましょう。
特定技能制度のメリット・デメリットまとめ
特定技能制度は、即戦力人材を柔軟に雇用できる制度として非常に有効ですが、支援義務や管理体制の構築が前提条件となります。
登録支援機関との連携や、技能実習との組み合わせなど、企業に合った制度運用を行うことで、外国人材との信頼関係を築き、長期的な雇用安定に繋げることが可能です。
2026年の制度改正にも対応しつつ、自社にとって最適な人材戦略の一環として活用を検討してみてください。