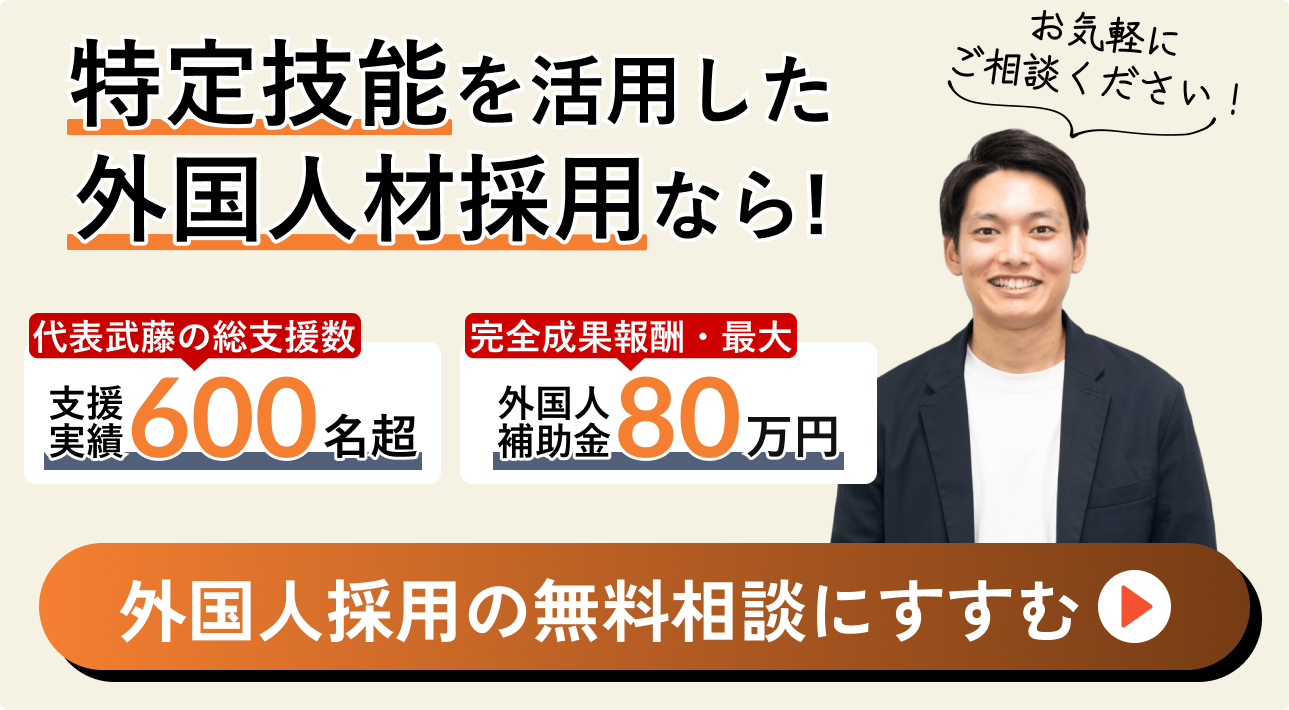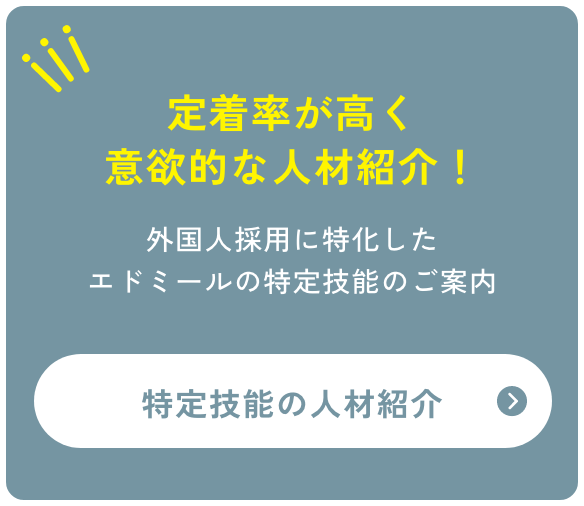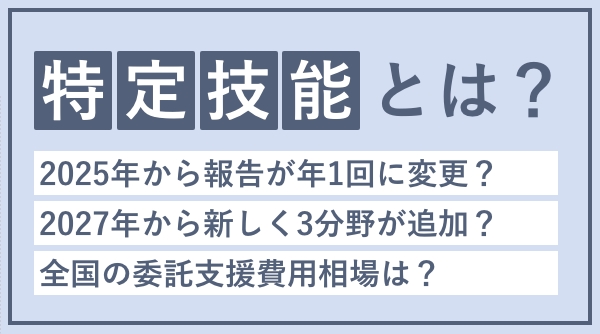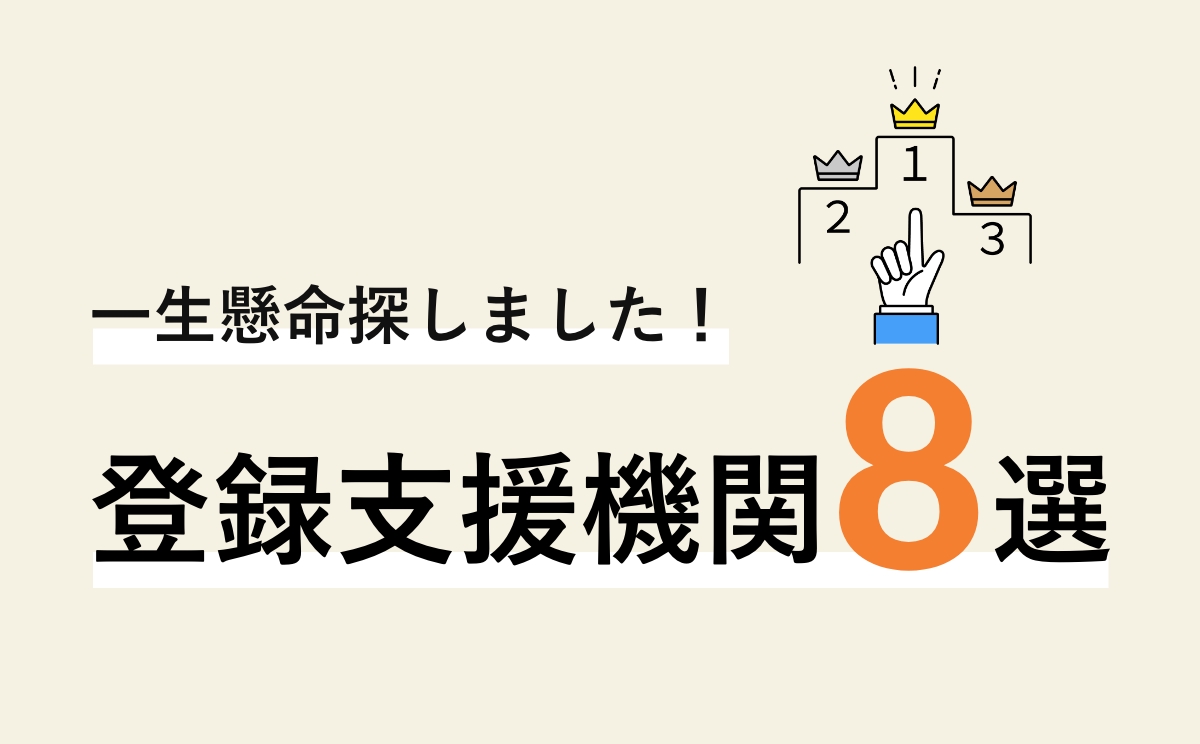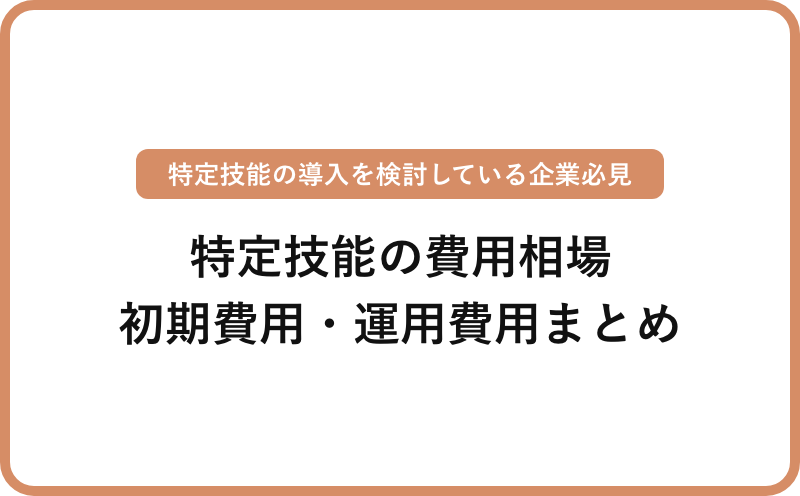【2026年版】特定技能の16職種一覧と要件を徹底解説|分野別試験・受け入れ条件も網羅
更新
特定技能制度は、日本国内の深刻な人手不足を背景に創設された外国人材受け入れ制度であり、即戦力として活躍できる外国人を対象に就労を許可する在留資格です。
制度開始から5年以上が経過し、2025年4月には対象分野が16分野に拡大されるなど、試験制度の整備や在留要件の見直しも含めて制度環境が大きく変化しています。
本記事では、特定技能制度の基本から、最新の対象職種・分野の情報、試験の種類、企業側の受け入れ要件まで、専門的に解説します。

合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢
2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。
武藤 拓矢のプロフィール特定技能とは何か?
「特定技能」は、2019年に創設された新たな在留資格で、一定の専門性・技能を持ち、即戦力として就労が可能な外国人材の受け入れを目的としています。
特定技能には以下の2種類があります:
- 特定技能1号: 16分野で就労可。在留期間は通算5年。家族帯同不可。
- 特定技能2号: 建設・造船の2分野(将来的に拡大予定)。在留期間の制限なし。家族帯同可。
技能実習修了者や日本語・技能試験合格者が主な対象であり、労働力不足を補う「即戦力人材」として期待されています。
特定技能の職種一覧(2025年4月時点)
2025年4月より、特定技能1号の対象分野は16分野に拡大されました。新たに「鉄道」と「林業」が追加され、以下が最新の一覧です:
| 分野名 | 主な職種・業務内容 |
|---|---|
| 介護 | 施設介護、通所介護、訪問介護など |
| ビルクリーニング | オフィスや施設の清掃、衛生管理 |
| 素形材産業 | 鋳造、鍛造、溶接、機械加工など |
| 産業機械製造業 | 機械組立、機械保全、検査 |
| 電気・電子情報関連産業 | 電子部品の組立・検査、製造 |
| 建設 | 型枠、鉄筋、内装仕上げ、電気通信など |
| 造船・舶用工業 | 溶接、仕上げ、塗装、鉄工など |
| 自動車整備 | 自動車の定期点検、故障修理、整備業務 |
| 航空 | 航空機地上支援業務(グランドハンドリングなど) |
| 宿泊 | ホテル・旅館でのフロント業務、清掃、接客 |
| 農業 | 作物・野菜・果物の栽培、収穫 |
| 漁業 | 沿岸・沖合での漁業作業、水産加工 |
| 飲食料品製造業 | 食品工場での加工・包装・品質管理 |
| 外食業 | 飲食店での接客、調理、店舗管理補助 |
| 鉄道 | 駅務、車両の清掃・点検・整備など |
| 林業 | 伐採、集材、森林整備など |
このうち、特定技能2号の対象は現在「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみですが、今後の拡大も検討されています。
特定技能の試験と要件
特定技能1号を取得するには、以下のいずれかを満たす必要があります:
- ① 分野別の技能評価試験に合格している
- ② 日本語能力試験(JLPT N4以上)または国際交流基金JFT-Basicに合格している
- ③ 技能実習2号を良好に修了している(同分野)
一部の国では、海外でも技能試験が実施されており、現地合格後に在留資格を申請して入国するケースも増加中です。
特定技能の受け入れ企業の要件
外国人を受け入れる企業側にも、以下のような要件があります:
- 社会保険・労働法令の遵守
- 日本人と同等以上の待遇(賃金・福利厚生)
- 支援体制の確保(自社支援または登録支援機関の活用)
- 支援計画書の作成と実施、記録保存
特に2026年以降は、支援記録の保存義務(1年以上)や年1回の定期届出が厳格化されており、企業のコンプライアンスがより重要視されています。
特定技能に関するよくある質問
Q. どの職種が人気ですか?
A. 介護、飲食料品製造業、建設、外食業が比較的人気ですが、国によっても偏りがあります(例:ネパールは介護、ベトナムは製造業)。
Q. 技能実習と特定技能の違いは?
A. 技能実習は「技能習得」が目的で監理団体経由、特定技能は「労働力受け入れ」が目的で企業との直接雇用となります。
Q. 特定技能の試験は難しいですか?
A. 分野や国によって異なりますが、介護・外食業などは比較的合格率が高く、日本語試験とセットでの対策が有効です。
Q. 職種をまたいで転職できますか?
A. 同一分野・職種内での転職は可能ですが、分野をまたぐ転職には改めてその分野の技能試験合格が必要です。
まとめ
特定技能制度は、2026年現在も継続的な制度改善と拡大が進められており、職種ごとの専門性や支援体制が受け入れの成否を左右する時代に入っています。
受け入れを検討する企業は、最新の分野情報、試験要件、外国人の国別特性を把握したうえで、信頼できる支援体制を整備することが重要です。