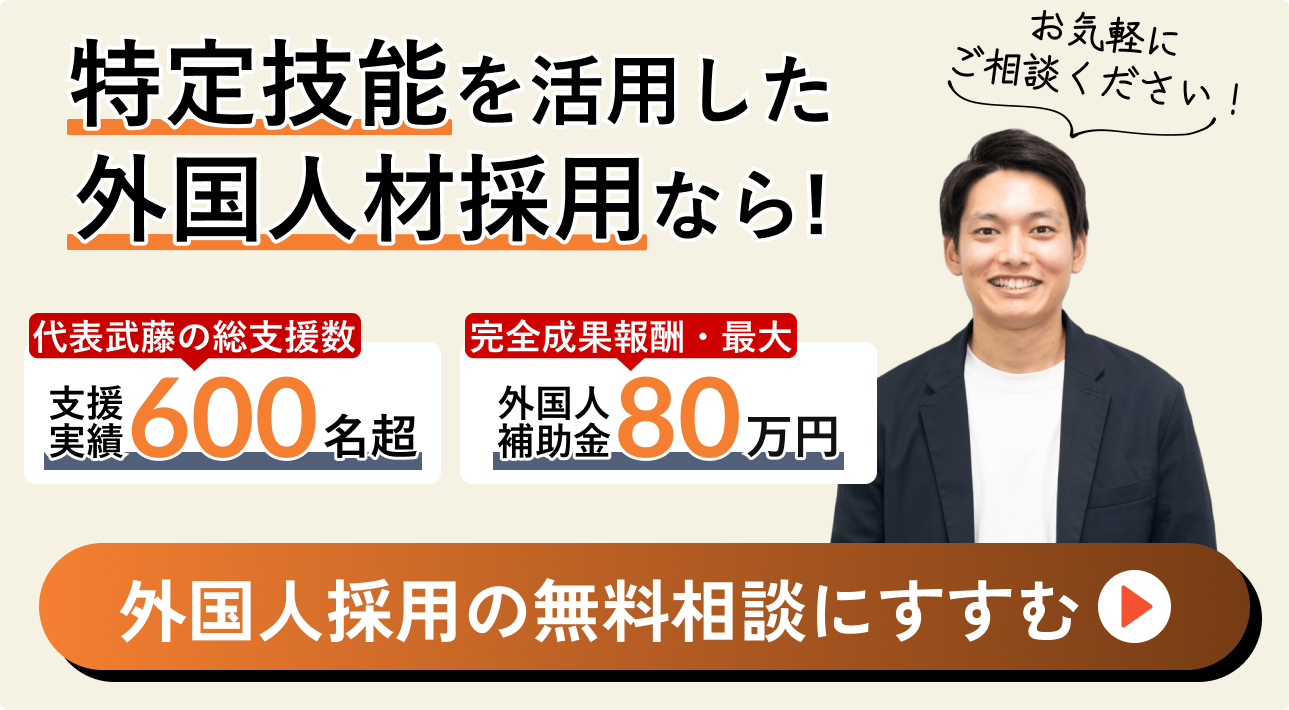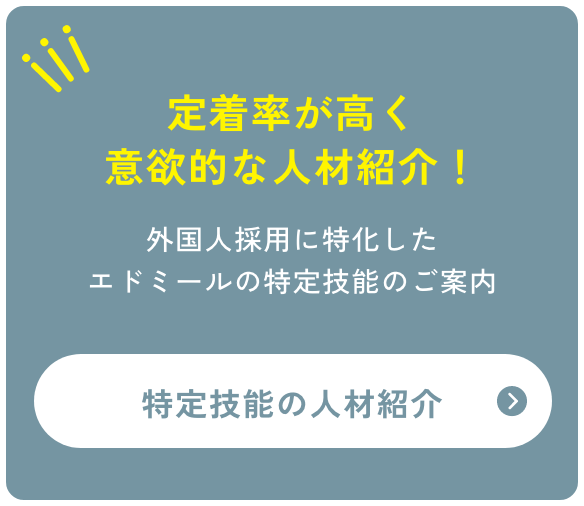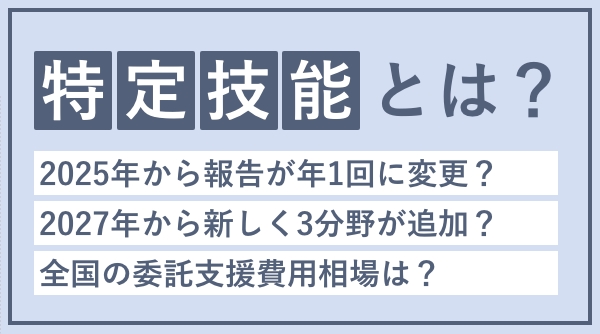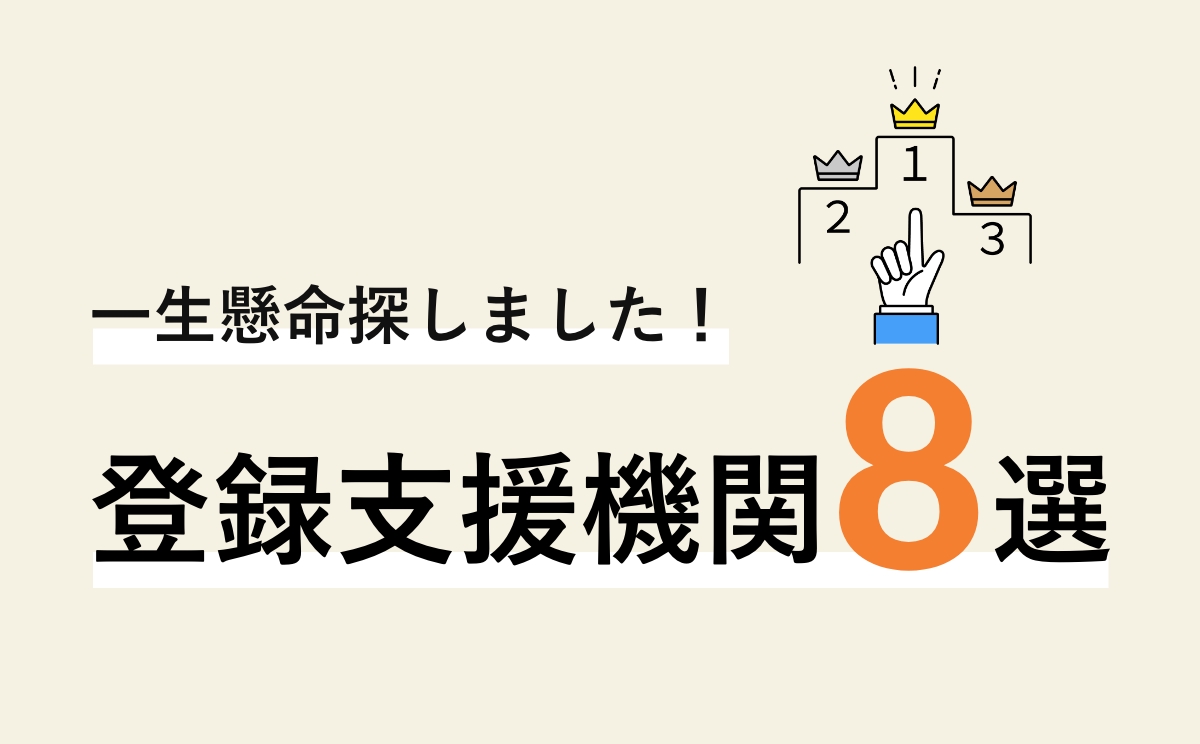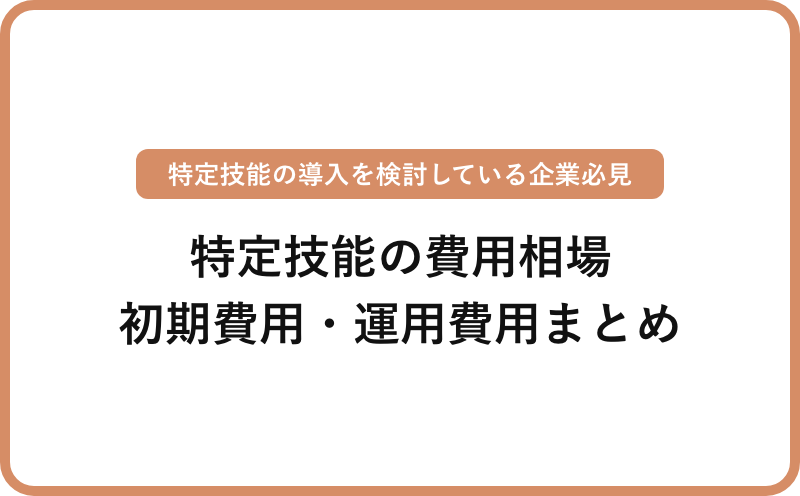【2026年最新版】特定技能と技能実習の違いを徹底比較|制度・目的・在留期間・転職・家族帯同まで
更新
外国人材の受け入れ制度として長年運用されてきた「技能実習制度」と、2019年に導入された「特定技能制度」。両制度の違いを正しく理解することは、適切な人材採用・管理に不可欠です。
この記事では、制度の目的・在留期間・業種・転職・家族帯同など、特定技能と技能実習の違いを表形式でわかりやすく比較し、2026年時点の最新情報をもとに徹底解説します。

合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢
2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。
武藤 拓矢のプロフィール特定技能と技能実習の基本理解
まず、両制度の概要を簡単に比較します:
| 項目 | 技能実習 | 特定技能 |
|---|---|---|
| 創設年 | 1993年 | 2019年 |
| 制度目的 | 技能移転による国際貢献 | 人手不足分野への即戦力人材の受け入れ |
| 在留資格 | 技能実習1号~3号 | 特定技能1号・2号 |
| 就労の自由度 | 限定的(実習先固定) | 転職可(同一分野内) |
特定技能と技能実習の目的の違い
技能実習制度は、「開発途上国への技術移転」を目的とした国際協力制度です。制度上は“労働”ではなく“実習”という位置づけになっています。
一方で、特定技能制度は「日本国内の人手不足解消」を目的とした在留資格であり、就労が前提の制度です。
就業可能な業種・業務の違い
対象分野は制度によって異なります。2025年現在の主な違いは以下の通りです:
- 技能実習: 約80職種(細分化された技能分類)
- 特定技能: 16分野(介護・建設・農業・外食など)
特定技能は、即戦力として日本国内で就労が可能な業務に限定され、明確な業種基準が設けられています。
在留期間の違い
- 技能実習: 最大5年(1号1年、2号2年、3号2年)
- 特定技能1号: 最大5年(更新可能)
- 特定技能2号: 制限なし(永住可能)
特定技能2号は、一定の熟練技能を持つ人材が対象で、家族帯同や長期在留が可能です。
転職の可否について
技能実習制度では、原則として転職は禁止されており、やむを得ない理由(廃業・虐待等)がある場合を除き、実習先を変更することはできません。
一方で、特定技能制度では、同一分野内での転職が可能であり、より柔軟な雇用形態が実現しています。
受入れ方法と人数の違い
- 技能実習: 原則として監理団体経由での受入れが必要
- 特定技能: 企業が直接雇用(支援業務は登録支援機関に委託可)
特定技能では、よりシンプルな受入れルートが用意されており、中小企業でも導入しやすい制度となっています。
家族帯同の可否
- 技能実習: 家族帯同は不可
- 特定技能1号: 帯同不可
- 特定技能2号: 帯同可(配偶者・子ども)
家族帯同の可否は在留資格により大きく異なり、長期的な人材定着を図るには2号の取得支援がカギとなります。
特定技能と技能実習の違いのよくある質問
Q. 特定技能と技能実習、どちらの方が自由度が高いですか?
A. 特定技能の方が転職・契約条件・在留更新の面で自由度が高いです。
Q. 技能実習から特定技能へ移行できますか?
A. はい。実習2号を良好に修了していれば、同分野であれば特定技能に無試験で移行可能です。
Q. どちらの制度が企業にとってメリットがありますか?
A. 長期的な人材確保を重視するなら、支援義務はあるものの特定技能の方が柔軟で持続性があります。
Q. 特定技能2号の取得は難しいですか?
A. 熟練技能を証明する試験合格が必要であり、受験者数も限られているため取得はハードルが高めです。
特定技能と技能実習の比較まとめ
特定技能と技能実習は、制度の目的・仕組み・自由度・定着性に大きな違いがあります。
技能実習は技術移転、特定技能は即戦力雇用という制度背景を正しく理解し、自社の人材戦略や支援体制に応じて最適な制度を選択しましょう。