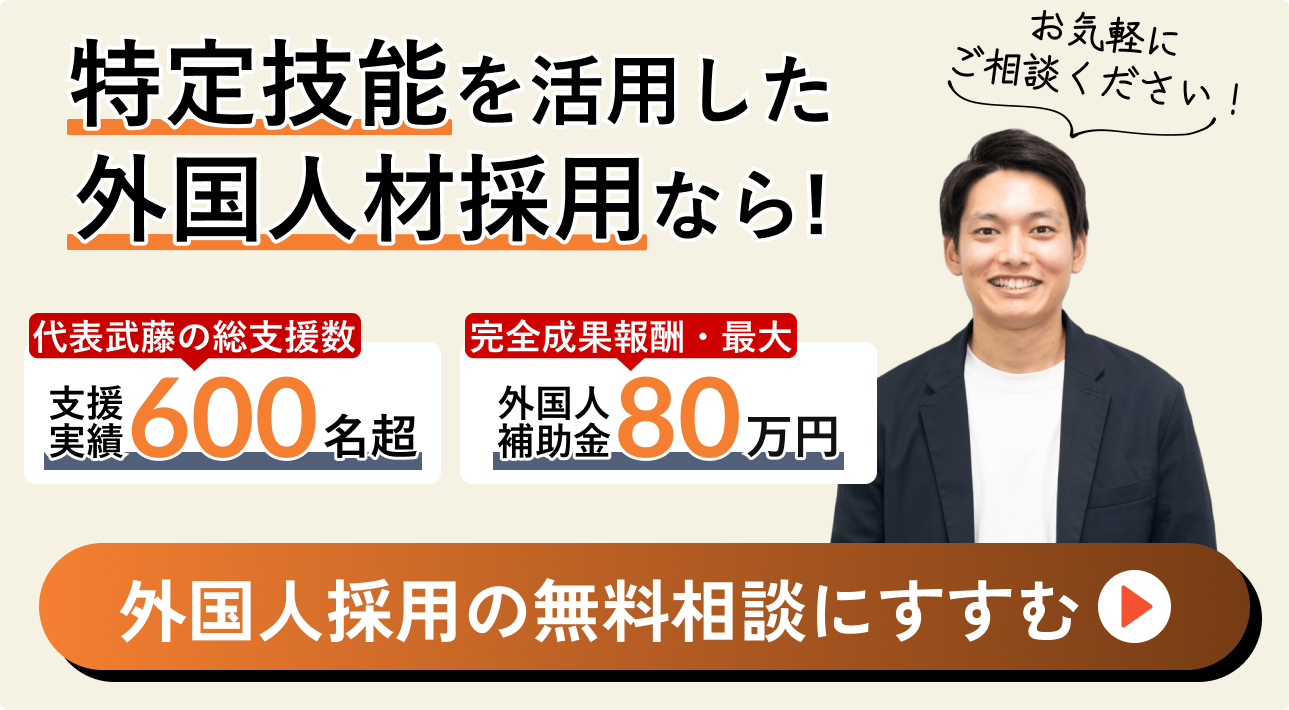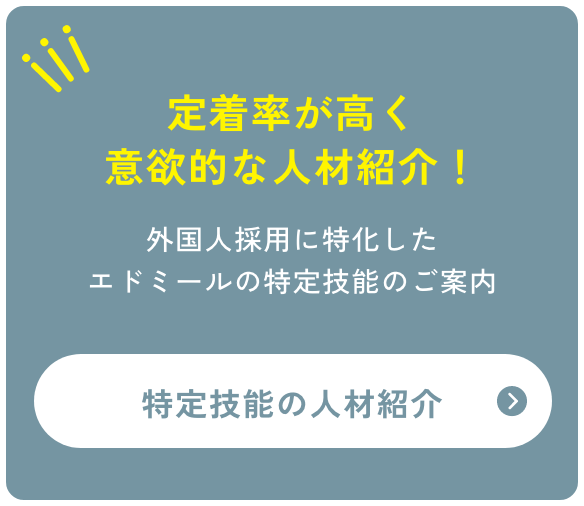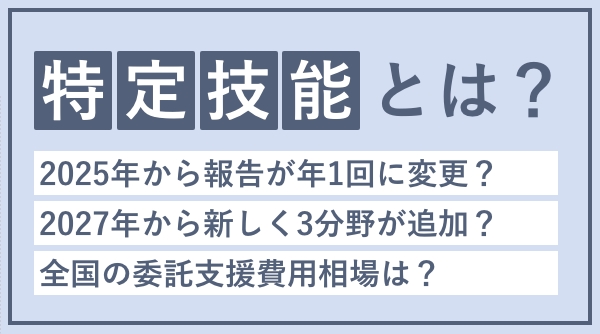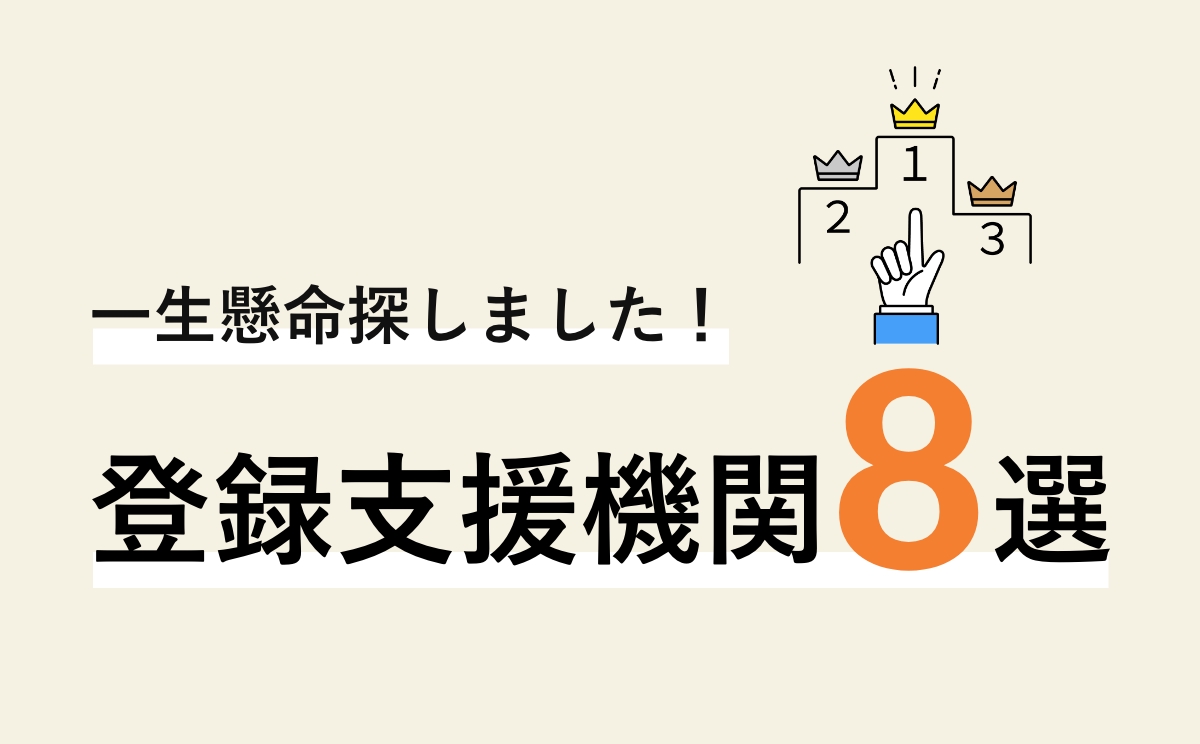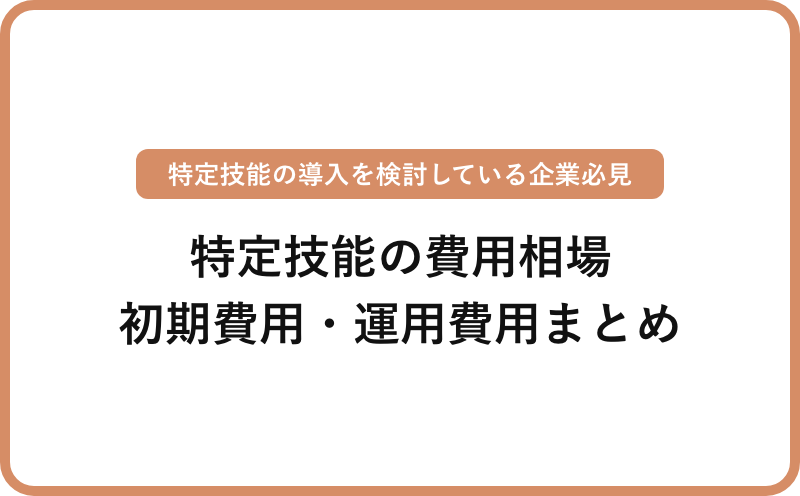特定技能外国人の離職理由とは?背景要因と分野別傾向、企業の対策を詳しく解説
更新
特定技能制度は、外国人が日本で中長期的に働くための在留資格制度として注目されています。しかし、制度開始から現在までに一定数の「離職」が発生しており、その背景を正しく理解することは、企業・支援機関にとって非常に重要です。

合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢
2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。
武藤 拓矢のプロフィール特定技能の離職率と統計
出入国在留管理庁の報告によると、制度開始から2022年11月末までに自己都合による離職者は約16.1%。制度全体で見ると、外国人の約8人に1人が自発的に離職している計算になります。
この数字は日本人の新卒3年以内離職率(約30%)と比べると低いものの、分野別に見ると差があり、特定の業種では離職率が20%を超えるケースもあります。
分野別の離職傾向
分野ごとの離職率を見ると、以下の傾向が見られます。
| 分野 | 離職率(自己都合) |
|---|---|
| 宿泊業 | 32.8% |
| 外食業 | 19.6% |
| 農業 | 20.1% |
| 飲食料品製造 | 19.3% |
| 介護 | 10.6% |
| 自動車整備 | 8.9% |
特に宿泊業や農業は、肉体的負担・人手不足・地方勤務の孤立感などから離職率が高い傾向にあります。一方、介護や自動車整備は比較的低めです。
離職理由①:業務・労働環境の不一致
「聞いていた仕事内容と違う」「業務量が想像以上に重い」「残業が多すぎる」など、就労環境へのミスマッチは主要な離職理由の1つです。
特定技能は即戦力採用であるため、現場は忙しい状況が多く、業務指導が十分にできないケースもあります。新人教育や労働環境の見直しが求められます。
離職理由②:給与・待遇への不満
外国人の多くは母国と比較して高収入を期待して来日しています。しかし、日本での生活コスト(家賃・社会保険・税金)を差し引くと、実質的な手取りが期待より少ないと感じる人も多くいます。
また、昇給制度が不透明であることや、ボーナス・残業代の不支給などが退職を考える要因となることもあります。
離職理由③:言語・文化の壁
職場での日本語使用が想定よりも高度で、業務指示が理解できない、同僚と円滑にコミュニケーションが取れないなどの理由で孤立感を抱くケースがあります。
また、日本独特の上下関係や報連相の文化に馴染めず、精神的なストレスを感じる外国人も少なくありません。
離職理由④:生活支援・人間関係の不足
初めて日本に来た外国人にとって、生活インフラの整備(住居契約、携帯、銀行口座など)は非常に負担です。支援が不足していると生活不安が増し、離職のきっかけになります。
さらに、職場での孤立、人間関係トラブル、パワハラなども離職に直結する要因です。
離職理由⑤:キャリアパスや将来の不安
特定技能1号は最長5年の在留が可能ですが、それ以降の進路(特定技能2号や永住)について説明が不十分なまま就労を開始する外国人も多くいます。
不透明な将来設計や、転職の自由度の低さ、家族帯同ができないことへの不安なども離職動機になります。
企業が行うべき離職防止策
- 求人票や面接時の条件提示を正確にし、期待値ギャップを埋める
- 入社後の定期面談を実施し、母語で悩みを聞ける体制を整備する
- 生活サポート(銀行口座開設、住宅探し、日本語研修)を支援する
- キャリアパス(特定技能2号や資格取得)を明示し、将来像を描かせる
- 人間関係の問題が起きやすい職場にはメンター制度や相談窓口を設置する
登録支援機関と連携して支援体制を強化することも非常に効果的です。
まとめ|離職理由を理解し、受け入れ体制を改善しよう
外国人が離職する背景には、複数の要因が絡んでいます。特定技能制度は、外国人が日本でキャリアを築く重要な制度であり、雇用側の努力によって定着率を高めることが可能です。
企業は単なる労働力確保だけでなく、支援者としての視点を持ち、外国人が安心して働ける環境づくりに取り組むことが求められています。