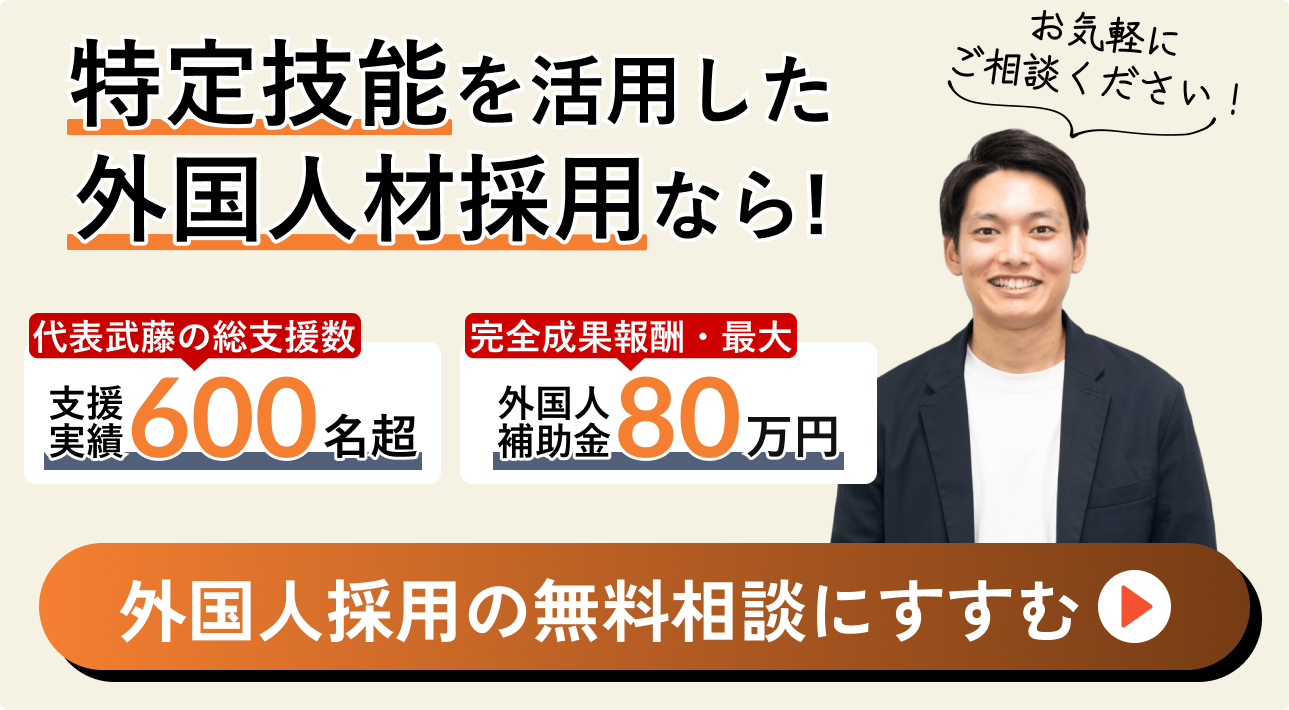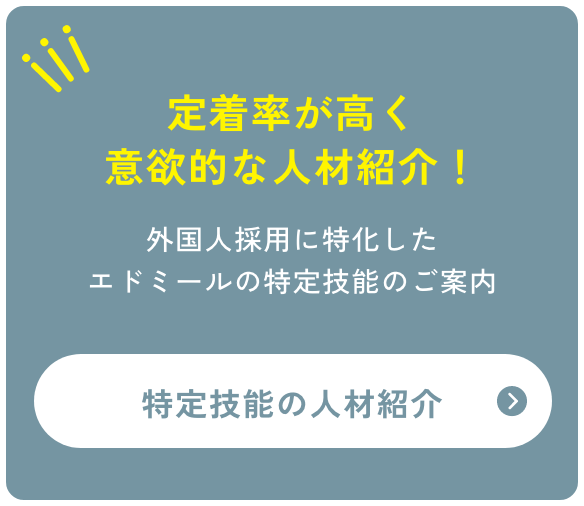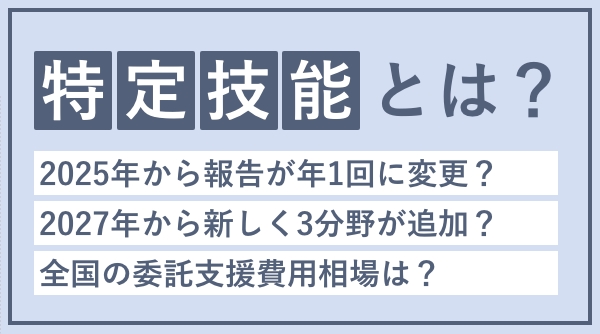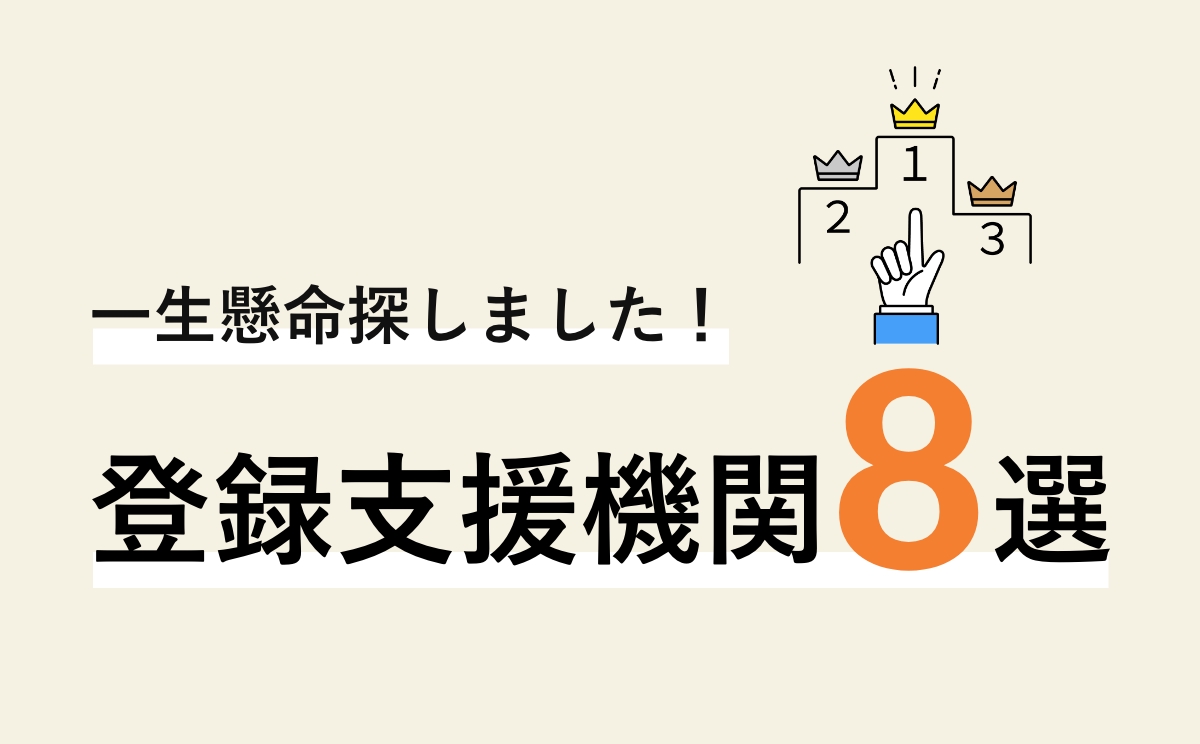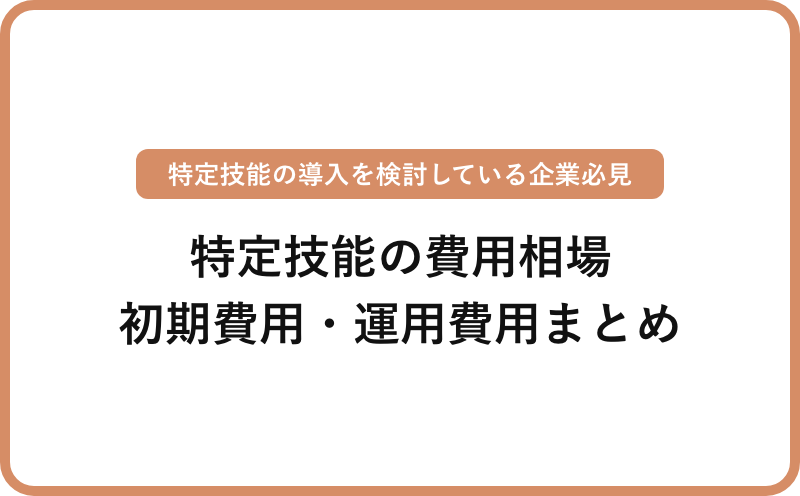【2026年版】特定技能外国人の離職率と定着対策を徹底解説|辞める理由・防止策・退職後の動向まで
更新
少子高齢化による人手不足を補う手段として活用されている「特定技能制度」。しかし実際には、採用後に早期離職してしまう外国人も一定数存在しています。
本記事では、特定技能外国人の離職率の現状や退職理由、離職を防ぐための対策や定着施策、さらに退職後の動向までを詳しく解説します。

合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢
2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。
武藤 拓矢のプロフィール特定技能外国人の離職率の現状
出入国在留管理庁が2024年度に公表したデータによると、特定技能外国人の離職率はおおむね年間10〜20%前後とされており、業種や国籍、受け入れ体制によって差があります。
- 離職率が高い:外食業、宿泊業、建設業など
- 離職率が低い:介護、製造業(食品・機械系)
特に制度導入初期における準備不足や、受け入れ企業・支援機関の体制不備が原因となるケースが目立ちます。
特定技能外国人が辞める主な理由
- ① 給与や労働条件への不満: 面接時とのギャップや長時間労働
- ② 人間関係の問題: 上司・同僚とのコミュニケーション不足、いじめ
- ③ 支援体制の不十分さ: 通訳不足、日本語が通じず孤立
- ④ キャリアへの不安: 将来の展望が持てず母国帰国を選択
- ⑤ より条件の良い企業へ転職: 制度上、分野内であれば転職可能
辞職の背景には、情報不足・支援不足・信頼関係の欠如が複合的に絡んでいることが多いです。
特定技能外国人の離職を防ぐための対策
1. 採用前の説明と期待値のすり合わせ
業務内容・給与・残業・寮費・生活支援の有無などを採用前に母国語で丁寧に説明し、誤解や不満を予防しましょう。
2. 定期面談・ヒアリング体制の強化
3か月に1回以上の定期面談を形骸化せず、本音を引き出せるよう通訳を活用した信頼関係づくりが必要です。
3. 日本人社員への教育
異文化理解やハラスメント研修を実施し、現場全体での受け入れ体制を整えることも離職防止につながります。
特定技能外国人の定着率を高めるための施策
- 日本語学習の支援(オンライン教材・日本語学校紹介)
- キャリア形成の支援(介護福祉士、技能検定などの支援)
- 地域交流イベントへの参加促進
- 休日や生活相談への対応窓口の明示
- 継続的な通訳・支援責任者の配置
「生活の安定」+「職場での安心」を両立させることが定着のカギです。
特定技能外国人の退職後の状況
特定技能外国人が退職した場合、以下のような動きがあります:
- 同分野内での転職: 新たな企業へ就職し、在留資格を継続
- 帰国: 再来日も可能(在留期限や分野による)
- 在留資格変更: 留学や配偶者ビザなどへ切り替える事例も
企業側が退職時の届出義務を怠ると、次回の受け入れに悪影響が及ぶ可能性もあるため注意が必要です。
特定技能外国人の離職率に関するよくある質問
Q. 特定技能の離職率はどれくらいですか?
A. 分野や国籍によりますが、一般的には10〜20%前後です。
Q. 外国人が辞める原因の1位は?
A. 労働条件の不一致、コミュニケーション不足が主な原因です。
Q. 離職後、他の会社で働けますか?
A. はい。同一分野内であれば転職は制度上認められています。入管手続きが必要です。
Q. 定着率を高めるにはどうすれば?
A. 支援体制の整備、日本語学習の支援、職場環境の改善などが効果的です。
特定技能の離職率まとめ
特定技能制度は、外国人材を安定的に受け入れるための制度ですが、離職リスクを前提に設計・運用することが重要です。
企業・支援機関が協力し、採用前から退職後までの一貫した支援体制を整えることで、外国人材の安心と信頼を得ることができます。