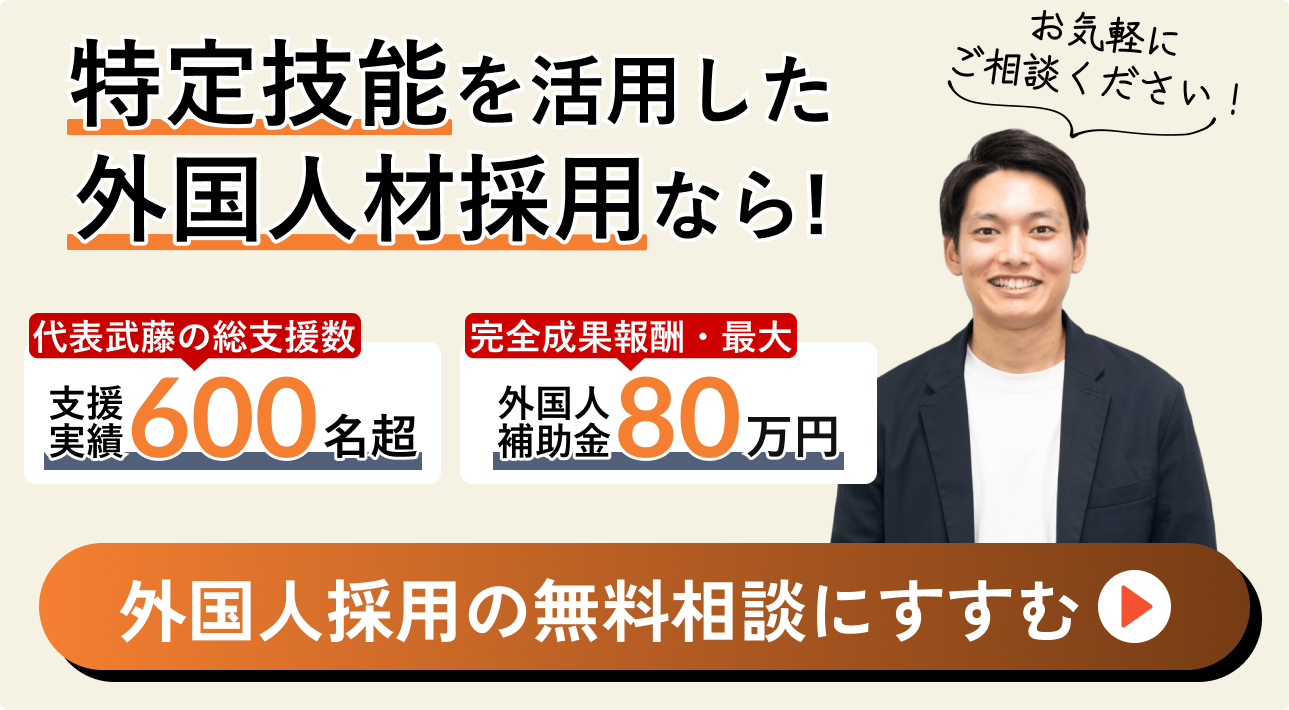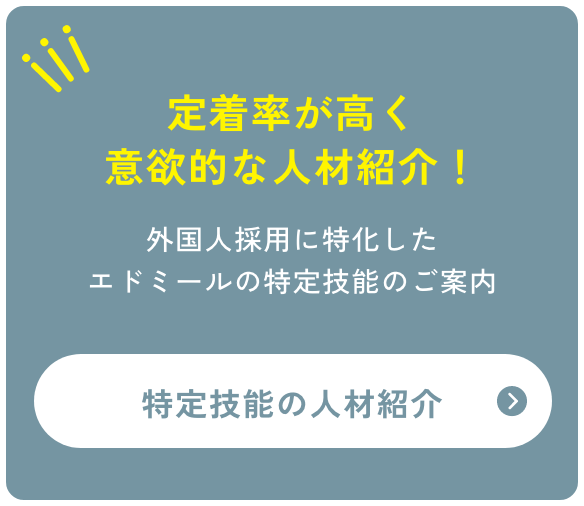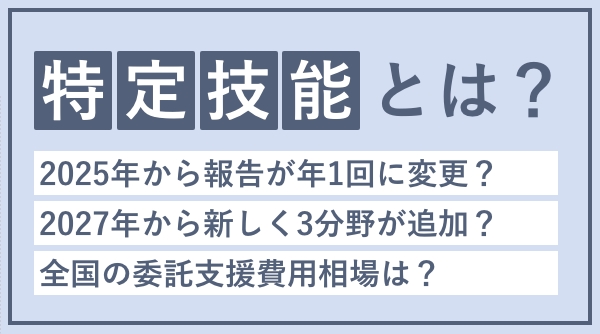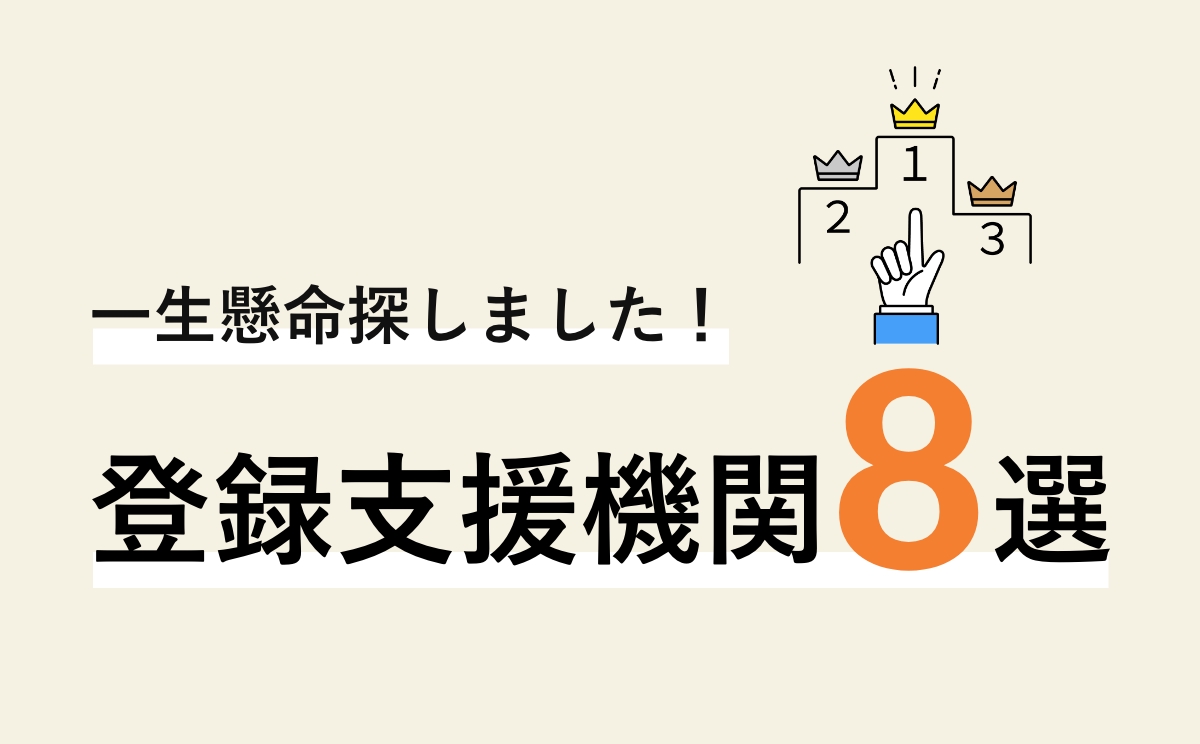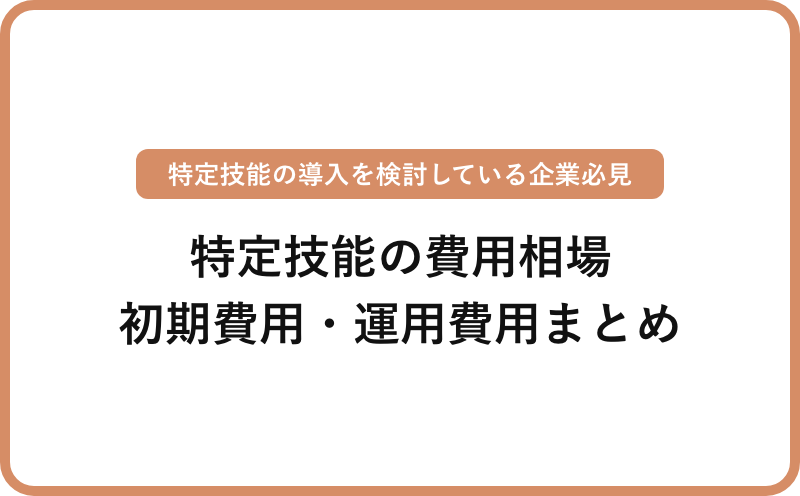【2026年版】特定技能ビザの申請方法・要件・更新手続きまで徹底解説|受け入れ企業向けガイド
更新
深刻な人手不足を補う制度として注目を集めているのが「特定技能ビザ(在留資格)」です。
本記事では、2026年の最新制度に対応した特定技能ビザの制度概要、取得要件、申請手続き、更新方法、そしてメリット・デメリットまで、企業担当者や登録支援機関向けにわかりやすく解説します。

合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢
2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。
武藤 拓矢のプロフィール特定技能ビザ制度の概要
特定技能ビザは、外国人が日本で就労するための在留資格の一つで、即戦力人材を対象に2019年に創設された制度です。
2025年4月時点で、以下の2種類が運用されています。
- 特定技能1号: 16分野に対応。在留期間は通算5年まで。家族帯同不可。
- 特定技能2号: 建設・造船など一部分野で許可。在留期間に上限なし。家族帯同可。
特定技能は、日本語と技能の一定基準を満たした外国人が対象で、技能実習修了者からの移行も広く活用されています。
特定技能ビザの申請手続き
外国人が特定技能ビザを取得するには、企業と外国人本人が協力しながら以下の手続きを行う必要があります:
- 人材の選定(試験合格者または技能実習修了者)
- 受け入れ企業側の事前確認書類の準備(支援体制・法令遵守の誓約書など)
- 支援計画書の作成(義務的支援10項目を網羅)
- 在留資格認定証明書交付申請(地方出入国在留管理局)
- 在留資格の交付・入国(または在留資格変更)
※すでに日本に在留している技能実習生は「在留資格変更申請」によって移行可能です。
特定技能ビザの取得要件
特定技能1号ビザの取得には、以下の要件を満たす必要があります:
- ① 日本語能力要件: JLPT N4以上、またはJFT-Basic合格
- ② 技能評価試験の合格: 分野ごとに定められた技能試験に合格
- ③ 健康・素行などの基準を満たす
なお、技能実習2号を良好に修了している場合は、試験免除での申請が可能です(同一分野に限る)。
特定技能ビザの更新と変更手続き
特定技能1号ビザは最大5年間の在留が可能で、1年・6か月・4か月ごとに更新が必要です。
更新手続きの流れ
- 契約更新・変更に応じた支援計画の修正
- 在留期間更新許可申請の提出(原則本人が行う)
- 支援の記録・実績書類を添付(面談記録など)
変更手続きの代表例
- 雇用先の変更(転職)
- 分野をまたぐ変更(再試験が必要)
- 登録支援機関の変更
更新・変更時も支援義務の履行状況が厳しく確認されるため、日常的な記録管理が非常に重要です。
特定技能ビザのメリットとデメリット
メリット
- 即戦力人材を外国から受け入れられる
- 技能実習より柔軟な制度(転職可、賃金も自由)
- 2026年時点で16分野と幅広い業種に対応
デメリット・注意点
- 支援義務が10項目あり、制度遵守に手間がかかる
- 書類不備や記録不足による不許可・行政指導のリスク
- 分野をまたぐ転職には再試験が必要
特定技能ビザに関するよくある質問
Q. 特定技能1号から2号へ移行できますか?
A. 建設・造船分野において、技能と実務経験を積めば可能です。要件や試験に関する最新情報は出入国在留管理庁の発表を参照してください。
Q. 日本語試験はN4必須ですか?
A. JLPT N4またはJFT-Basicが目安ですが、技能実習修了者は免除されます。
Q. 自社で支援業務を行う必要がありますか?
A. 自社支援でも登録支援機関への一部・全部委託でも構いません。支援体制が整っていれば、いずれも可です。
Q. ビザの更新時に面談記録の提出は必要ですか?
A. はい。定期面談の記録は1年以上保存が必要で、更新時に支援実績として提出を求められることがあります。
まとめ
特定技能ビザは、日本の労働力不足を解決するための有力な制度として、今後さらに活用が広がると期待されています。
一方で、制度の趣旨や支援義務、更新手続きの正確な理解がなければ、不許可・指導・受け入れ停止といったリスクもあります。
2026年の制度改正を踏まえた最新情報を常にチェックしつつ、外国人材と企業が互いに信頼し合える関係を築くための制度運用を心がけましょう。