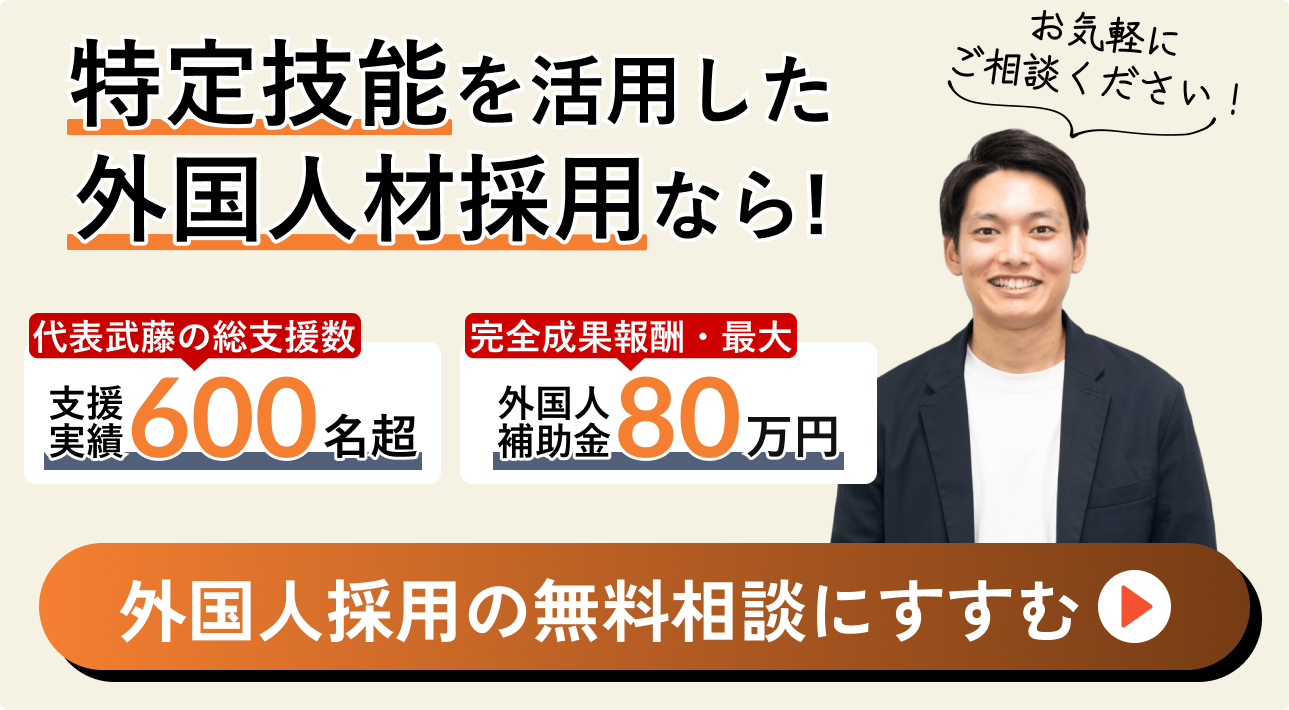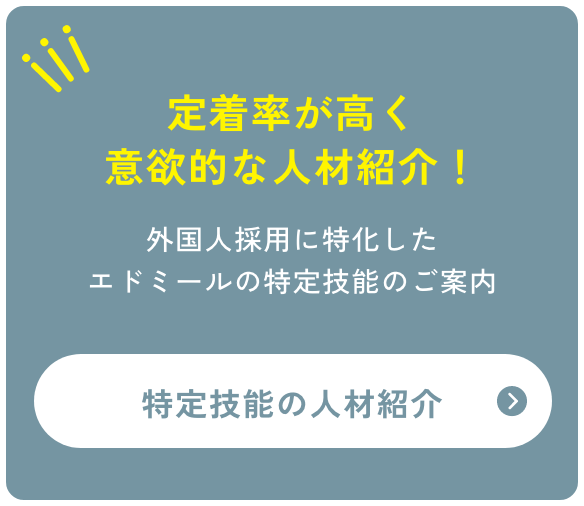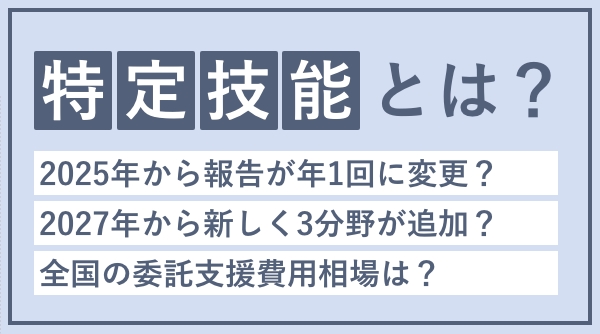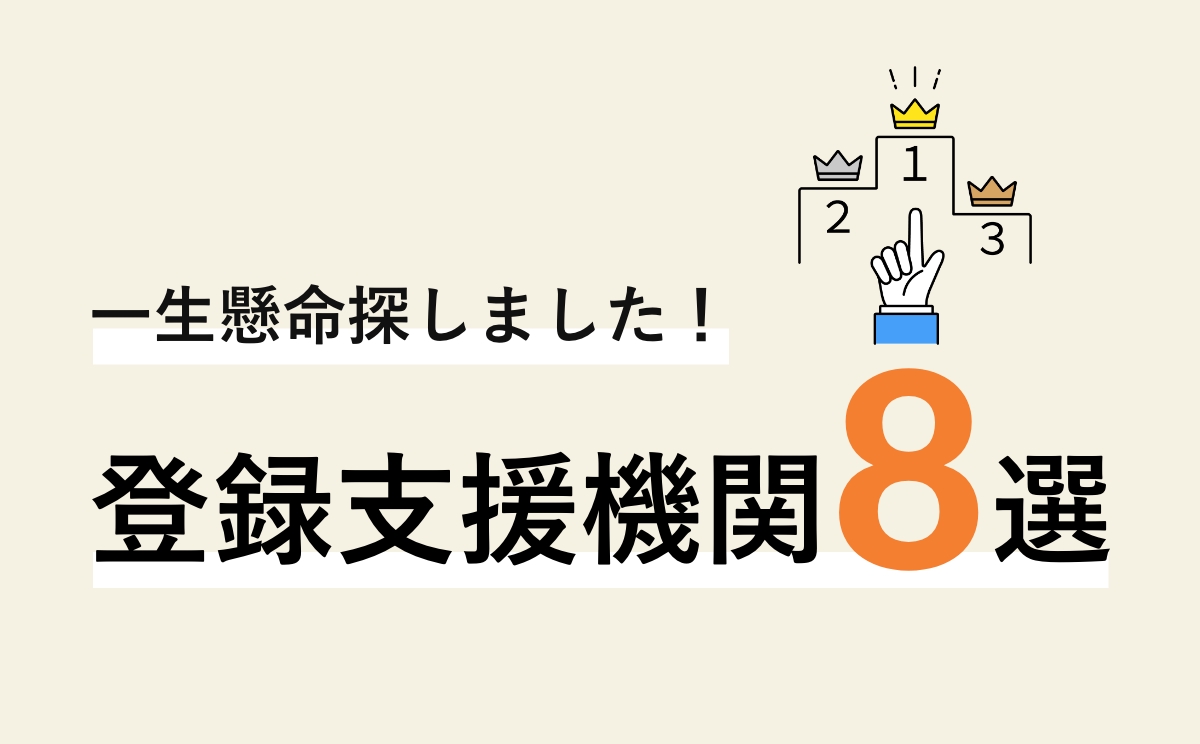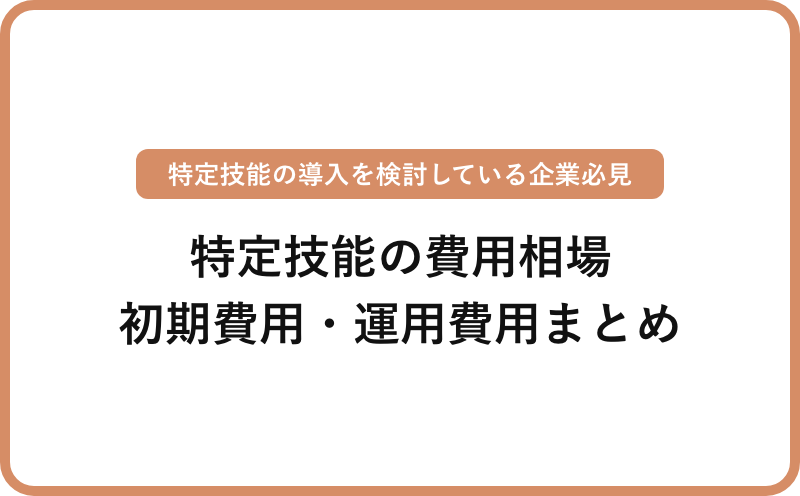【2026年対応】監理団体と登録支援機関の違いとは?制度・役割・選び方まで徹底解説
更新
「監理団体と登録支援機関って何が違うの?」「うちの会社が使うのはどっち?」
外国人材の受け入れを検討している企業にとって、この2つの制度は混同しやすく、判断に迷うポイントです。
この記事では、技能実習と特定技能という異なる在留資格を支える「監理団体」と「登録支援機関」について、制度背景から業務内容、選び方までわかりやすく解説します。

合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢
2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。
武藤 拓矢のプロフィール監理団体と登録支援機関の基本的な理解
両者の大きな違いは、対象となる在留資格です。
- 監理団体:技能実習生を対象に監督・支援を行う団体(非営利法人)
- 登録支援機関:特定技能外国人に対して生活・就労支援を提供する民間機関
制度的にも、技能実習は「育成・送り出し型」、特定技能は「即戦力・雇用型」と異なる位置づけで設計されており、制度そのものが異なるため両者の役割も異なります。
監理団体の機能と業務内容
監理団体は、技能実習制度において受入企業を指導・監督する非営利法人です(事業協同組合などが該当)。主な役割は以下の通りです:
- 技能実習生の生活支援・相談対応
- 実習計画の作成・提出支援
- 企業への訪問指導(3か月に1回以上)
- 不適切な実習環境への是正勧告
- 入管庁・OTITへの報告業務
実習生と企業の間に立ち、制度運用を適正に行う監査的役割を担っているのが特徴です。
登録支援機関の具体的な支援内容
登録支援機関は、特定技能外国人を受け入れる企業から委託を受けて、義務的支援10項目を実施する機関です。2026年時点では、以下のような支援が求められます:
- 事前ガイダンス(母国語での就労条件説明)
- 住居の確保・契約支援
- 生活インフラ(銀行・携帯など)の契約支援
- 出入国時の送迎
- 日本語学習の機会提供
- 定期面談の実施と記録(3か月に1回)
- 年1回の定期届出(2025年より改正)
技能実習と異なり、雇用主と外国人が直接雇用関係にある点も特定技能の特徴で、登録支援機関はその雇用関係を支援する形になります。
監理団体と登録支援機関の違い
| 項目 | 監理団体 | 登録支援機関 |
|---|---|---|
| 対象制度 | 技能実習 | 特定技能 |
| 法人形態 | 非営利法人(協同組合など) | 民間企業・NPOなども可 |
| 契約関係 | 監理団体⇔受入企業 | 受入企業⇔登録支援機関 |
| 役割 | 監督・指導・生活支援 | 生活・就労支援 |
| 行政提出物 | 技能実習計画、報告書など | 支援計画書、定期届出など |
監理団体と登録支援機関の選び方
制度が異なるため、併用することはできません。企業が受け入れたい外国人が、
- 技能実習生の場合 → 監理団体を通じて受け入れ
- 特定技能外国人の場合 → 登録支援機関との契約が必要
特定技能への移行が増えている現在、登録支援機関は日本語サポート体制、支援実績、対応国籍などを比較検討しましょう。
監理団体と登録支援機関に関するよくある質問
Q. 技能実習から特定技能へ移行する際、監理団体の関与はどうなりますか?
A. 技能実習を修了した外国人が特定技能へ移行した場合、監理団体との関係は終了し、登録支援機関との新たな契約が必要になります。
Q. 登録支援機関は誰でもなれますか?
A. 一定の要件(外国人対応経験、体制、過去の法令違反がないなど)を満たし、出入国在留管理庁に登録申請・許可を受けた事業者のみが登録支援機関になれます。
Q. 両方を同時に使うことは可能ですか?
A. できません。技能実習と特定技能は異なる制度であるため、監理団体と登録支援機関の併用は不可です。
まとめと今後の展望
監理団体と登録支援機関は、制度の目的・支援範囲・関係性が大きく異なります。混同を避け、受け入れ制度ごとの役割を正確に理解することが、外国人材の適正活用につながります。
2026年現在、技能実習から特定技能への移行が急増しており、登録支援機関の重要性は今後さらに高まると見られています。
貴社の受け入れ制度に応じて、最適な支援体制を選び、外国人材の定着と活躍を支える体制構築を進めましょう。