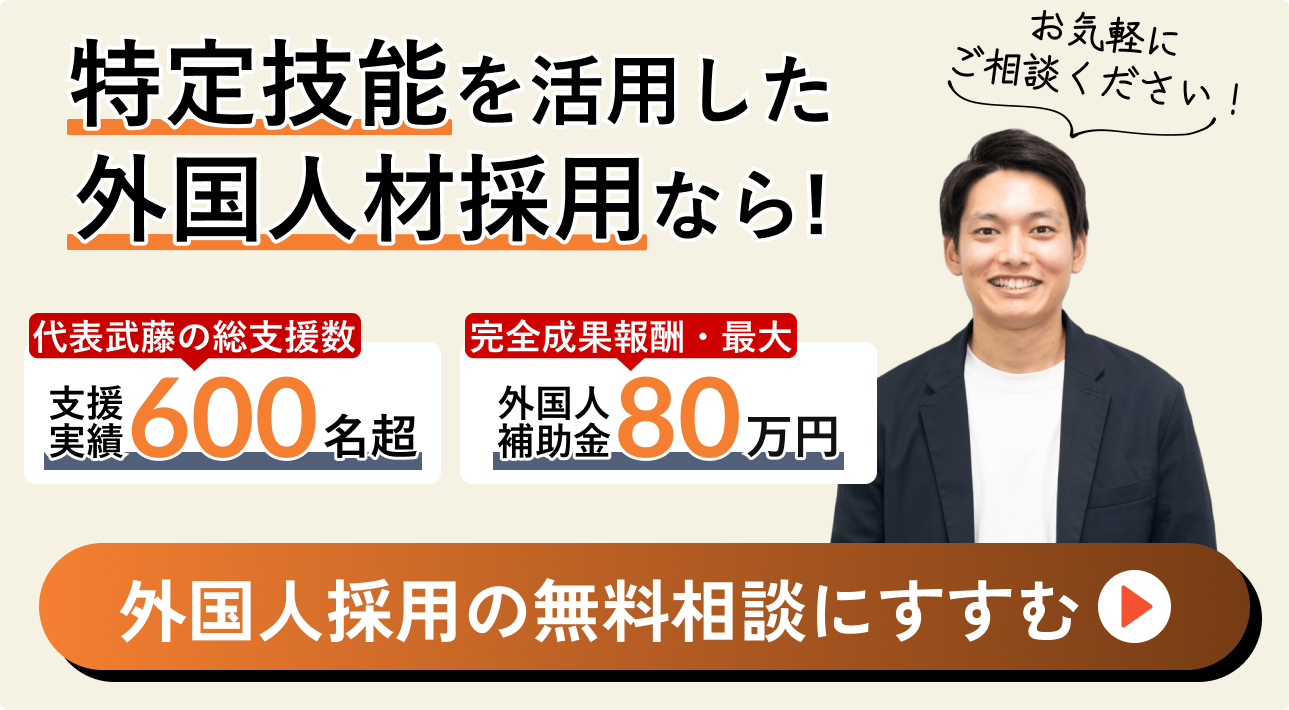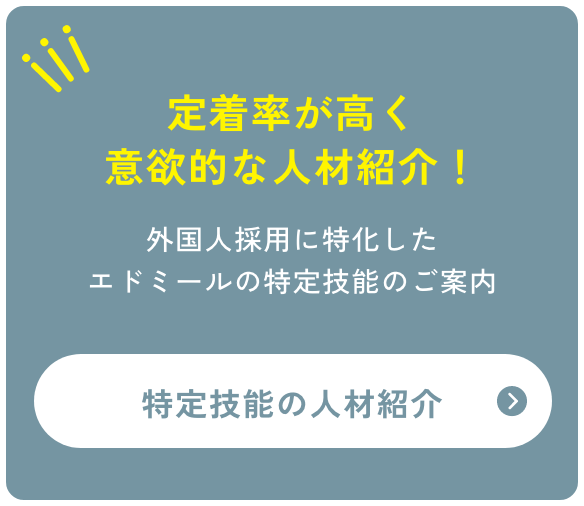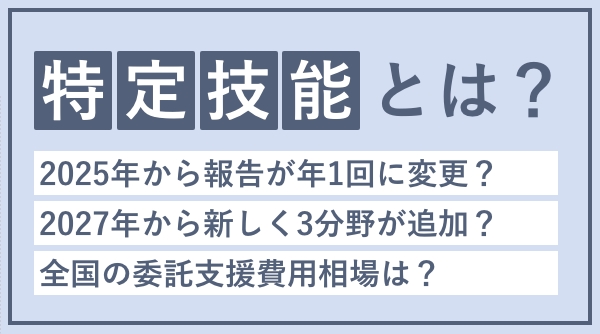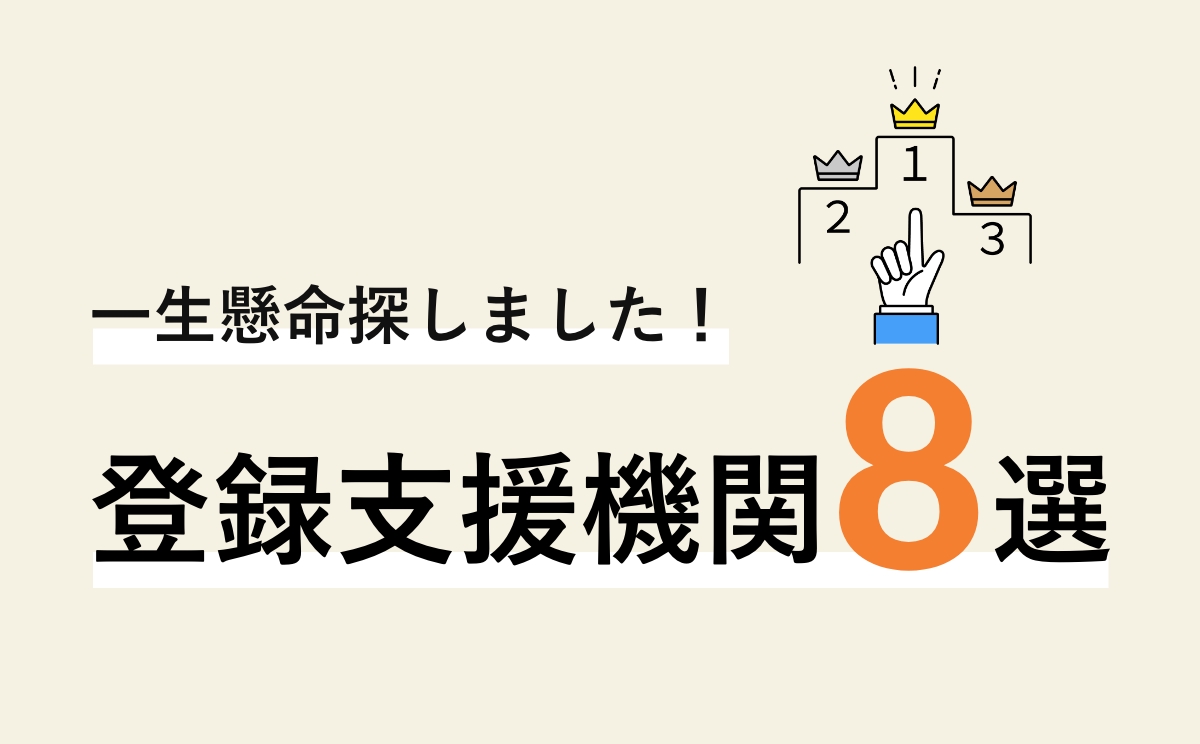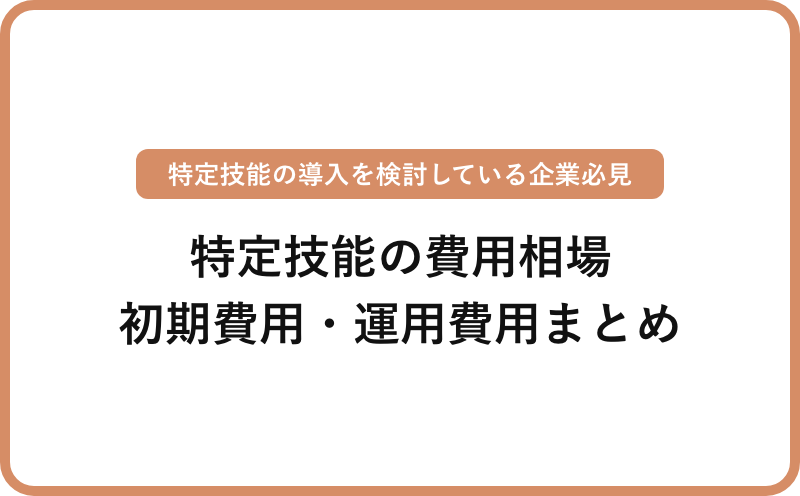育成就労制度とは?施行スケジュール・制度設計・移行要件を最新情報で徹底解説
更新
育成就労制度は、技能実習制度に代わり2027年4月に施行予定の新たな在留資格制度です。外国人を「育成」と「就労」の両面で支援し、特定技能1号への円滑な移行を設計しています。2025年7月現在、制度の施行スケジュールから受け入れ分野、要件、企業の準備ポイントまで最新動向を詳しく整理しました。

合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢
2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。
武藤 拓矢のプロフィール制度創設の背景と施行スケジュール
2019年から続く技能実習制度は、本来の目的である国際貢献と実態に乖離があり、労働者保護上も課題が残っていました。有識者会議や閣僚会議の議論を経て、改正入管法・育成就労法が2024年6月に成立し、2027年4月に施行される予定です。施行までに3年以内の準備期間が設けられ、現行制度との併存期間も考慮されています。
政府は2025年2月〜5月にかけて有識者懇談会や基本方針の策定、分野別運用要項の作成を進めています。最終方針は2025年12月頃に確定予定で、監理支援機関の許可申請開始や人材受け入れ体制整備が急務となります。
対象分野と在留期間・転籍制度
育成就労制度は、介護・建設・農業・製造・外食業など、特定技能対象の17〜19分野で運用されます。政府案では物流や鉄道など新分野も含め17分野が検討されており、最終的には特定技能制度と合わせて最大19分野になる見込みです。
在留期間は原則3年以内。転籍は同一業務区分かつ所定勤務期間・日本語能力・技能条件を満たす場合、本人希望による転籍が可能で、制度の柔軟性が従来に比べ大幅に向上しています。
日本語・技能要件と試験体制
就労開始時には日本語能力A1(N5相当)以上の試験合格または講習修了が必要。1年経過時には技能検定基礎級と日本語A1〜A2相当の試験に合格が求められます。特定技能1号への移行時にはJLPT N4(またはJFT-Basic A2)以上の日本語能力と技能検定3級等の合格が条件です。
不合格者には最長1年の在留延長が認められ、再挑戦機会が用意されています。2025年5月には制度設計にあたり技能実習試験の活用案も提示され、移行手続きの円滑化が期待されています。
制度設計の大きな特徴
- 技能実習制度では不可だった本人希望転籍が原則認められる
- 民間職業紹介事業者による斡旋は禁止され、監理支援機関やハローワークによる認定・監督が義務付けられる
- 育成就労計画の認定制導入により、受け入れ実施者ごとに計画作成と認定が必要
- 監理支援機関は許可制に改められ、営利団体の運営は不可。非営利組織が対象
企業にとってのメリットと留意点
企業にとっては、外国人材を長期的に確保でき、日本語や技能の研修体制を構築することで定着率の向上が期待できます。育成と就労がセットになった設計のため、計画的な人材育成を行う企業には有利です。
一方で、制度導入には初期導入コスト(研修・人材マネジメント体制整備)や認定申請手続きの負担、運用要件の変動リスクが伴います。MOC未締結国からの受け入れ制限や送出機関の適正管理など、新たな法律運用にも注意が必要です。
企業が今から取り組むべき準備ポイント
- 育成就労計画運用フローの社内整備と監理支援機関候補の選定
- 日本語教育や技能訓練プログラムの設計・導入
- 監理支援機関との契約準備(非営利団体としての対応確認)
- 受け入れ分野の最終決定に伴う採用領域の再構築
- 送出国のMOC状況確認と適正送出ネットワークの構築
まとめ|育成就労制度の全体像と戦略的活用視点
育成就労制度は、特定技能1号への道筋を制度設計で明確にしつつ、育成と就労を両立させる新しい外国人雇用制度です。制度施行に向けたスケジュールや要件調整が進む中、企業は事前準備と運用体制の整備が求められます。
今後は制度詳細の確定や分野別運用要領の発表が続くため、最新情報のフォローと柔軟な制度対応が、外国人材活用や定着の鍵となります。